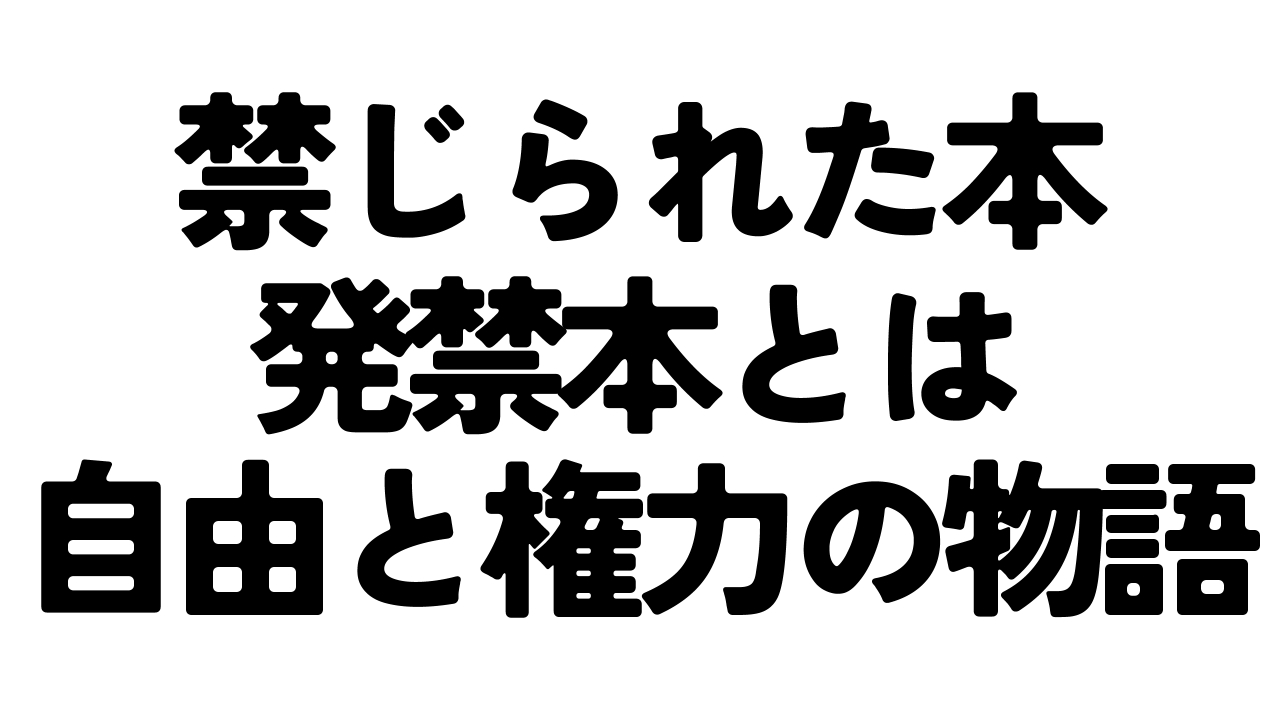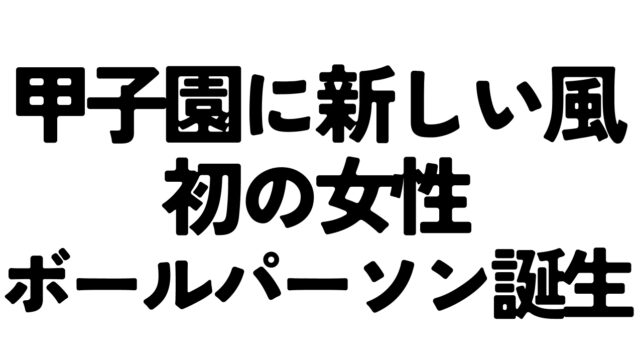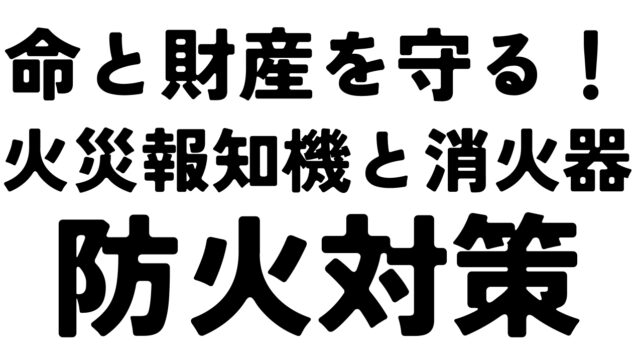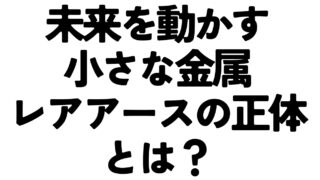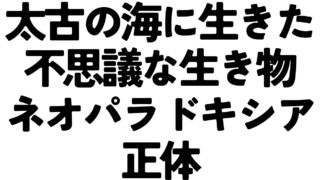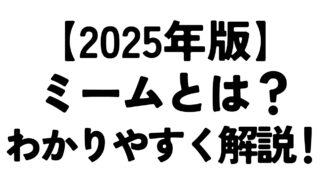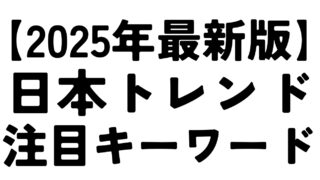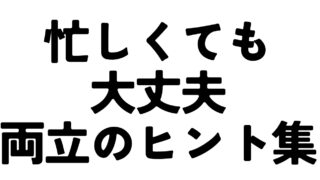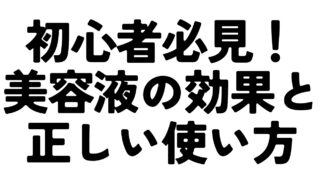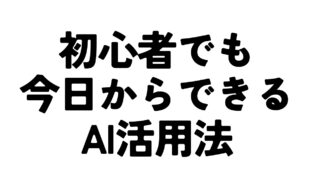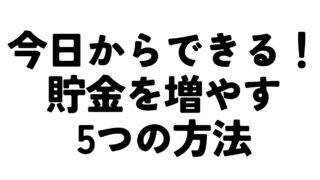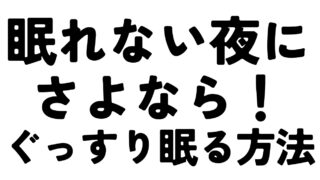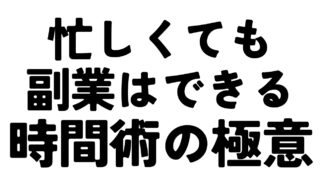本好きな人や歴史好きの人なら一度は耳にしたことがある「発禁本(はっきんぼん)」。文字通り「発行禁止になった本」のことですが、なぜ禁止されたのか、その背景には常に政治・宗教・社会規範が存在します。この記事では、発禁本の意味、歴史、有名な禁書、そして現代社会における発禁のあり方について初心者にもわかりやすく解説します。
発禁本とは?
発禁本とは、国家や宗教、司法の判断によって発行や販売、流通が禁止された本のことです。「発禁=発行禁止」の略語であり、海外では「禁書」とも呼ばれます。
禁止される理由はさまざまですが、大きく分けると以下の3つです。
- 政治的理由:政府批判や反体制的思想を広める可能性がある
- 宗教的理由:教義を否定したり異端とされる内容を含む
- 倫理・風俗的理由:わいせつ・残虐・反社会的とされる
日本における発禁本の歴史
江戸時代の出版統制
江戸幕府は、政治批判や風刺を含む書物を厳しく取り締まりました。特に「洒落本」や「黄表紙」など庶民の娯楽本も、幕府に都合が悪いと発禁になりました。
明治〜大正時代
内務省が検閲を行い、社会主義や無政府主義の思想書は次々と発禁に。夏目漱石や森鴎外などの文豪の作品も、一部表現が問題視され削除や修正を命じられることがありました。
戦時中
軍国主義体制の下で検閲はさらに厳格化。反戦的な思想や外国文化を賛美する本は徹底的に排除されました。新聞記事さえ削除されることが多く、「発禁本」のピークともいえる時代です。
戦後〜現代
1947年の日本国憲法で「検閲の禁止」が定められ、基本的に発禁制度はなくなりました。しかし、裁判所が「わいせつ図書」と認めた場合には販売禁止になることがあります。
海外における禁書の歴史
中世ヨーロッパと「禁書目録」
カトリック教会は、宗教改革や科学的思想に脅威を感じ、**「禁書目録(Index Librorum Prohibitorum)」**を作成。ガリレオ・ガリレイの著作や、コペルニクスの地動説関連書も禁止されました。
近代以降
- ジョージ・オーウェル『1984』:全体主義を批判したため、一部の国で禁止
- アンネの日記:歴史的背景から、国や地域によって規制されることがある
- サルマン・ラシュディ『悪魔の詩』:イスラム教への冒涜とされ、発禁どころか暗殺指令が出された
禁書は「思想の自由」と「社会秩序」のせめぎ合いを象徴しています。
有名な発禁本・禁書の例
日本
- 太宰治『新ハムレット』:戦時中に反戦的と判断され発禁
- 三島由紀夫『禁色』:同性愛描写が問題視され、一部地域で販売中止
- 大江健三郎『性的人間』:わいせつ性が争点となり裁判へ
海外
- 『ユリシーズ』(ジェームズ・ジョイス):性描写が露骨すぎるとしてアメリカで長らく禁書
- 『ガリヴァー旅行記』(ジョナサン・スウィフト):権力批判が強いため検閲対象に
現代社会における発禁本
紙の本から電子書籍へ
インターネットの普及で、「発禁」にしても完全には流通を止められない時代になりました。電子書籍やPDFで拡散され、かえって注目を集めることもあります。
発禁の新しい形
現代では「国家による禁止」よりも、
- プラットフォーム(Amazon、Appleなど)による配信停止
- 出版社による自主規制
が実質的な「発禁」の役割を担っています。
発禁本が持つ意味
発禁本は、単なる「危険な本」ではありません。むしろ、権力にとって不都合な真実や、新しい価値観を提示する本であることが多いのです。
歴史を振り返れば、かつて発禁だった本の多くが今では「古典」や「名著」として評価されています。つまり発禁本は、時代の価値観と自由の境界線を映し出す鏡ともいえるでしょう。
まとめ|発禁本から見える社会と自由
- 発禁本とは「発行・販売が禁止された本」のこと
- 日本では江戸時代から戦時中まで厳しい出版統制が行われた
- 海外では宗教や思想統制の一環として多くの名著が禁書に
- 現代では検閲は原則禁止だが、わいせつや自主規制での販売中止は存在する
- 発禁本は、時代ごとの「権力と表現の自由」の関係を映す存在
発禁本を知ることは、言論の自由や社会の変化を理解するための貴重な手がかりとなるのです。
この記事は個人で収集した情報をもとに記載していますので、誤った情報を記載している可能性があります。
この記事だけではなく、他の方が公開されている情報もぜひチェックしてみてください