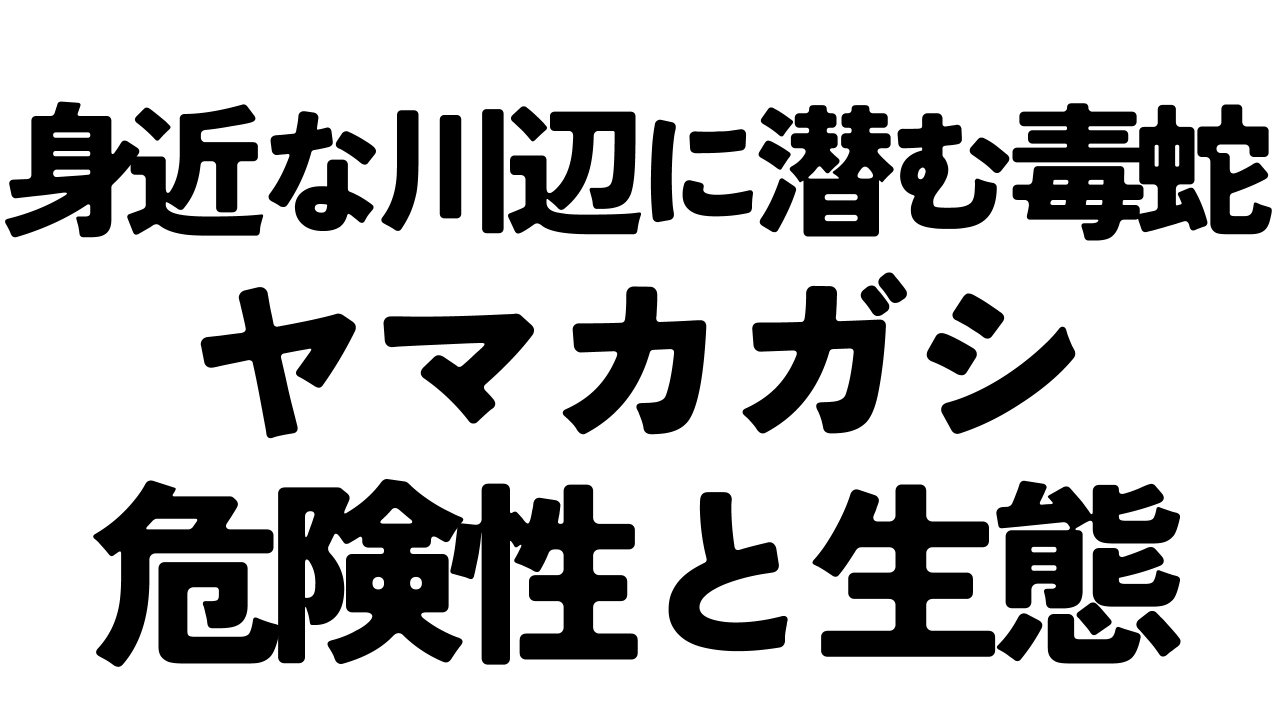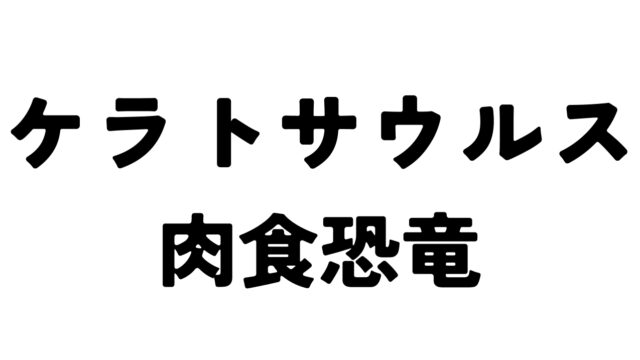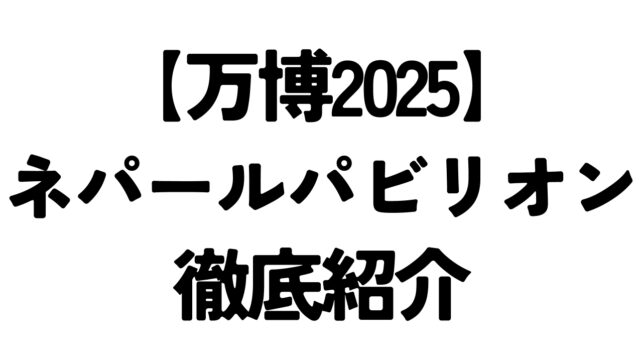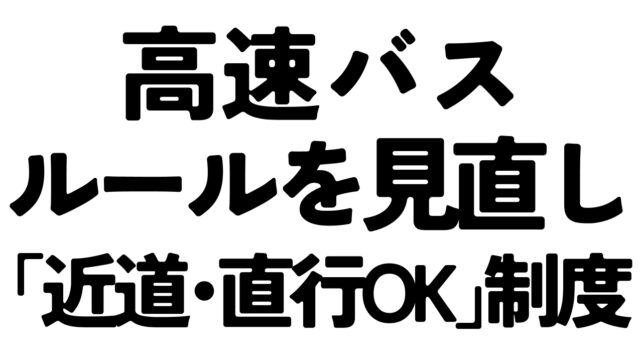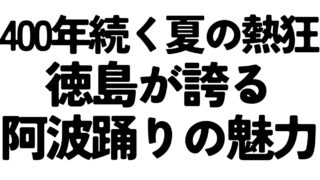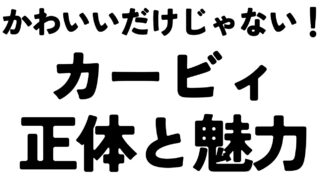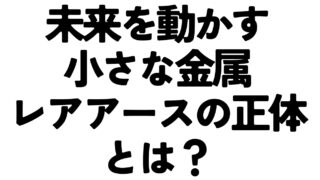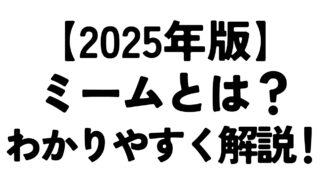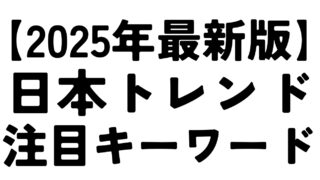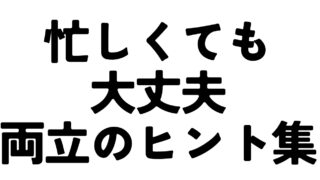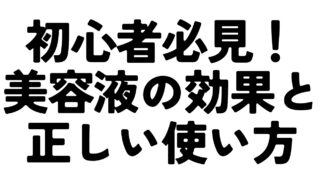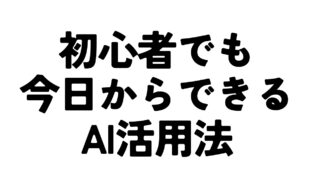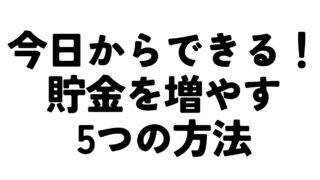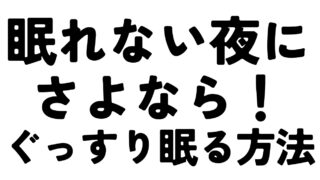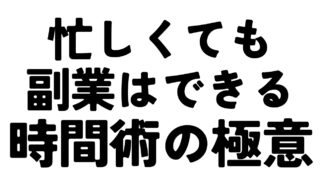日本に生息する毒蛇といえば、多くの人が思い浮かべるのは マムシ や ハブ ではないでしょうか。ところが、実は身近な場所に生息しながら、意外と知られていない毒蛇がいます。それが ヤマカガシ です。
ヤマカガシは全国各地の田んぼや川辺、公園の水辺などにも生息しており、実は私たちの生活圏と近い存在です。その見た目から「無毒の蛇」と誤解されることもありますが、実際には強力な毒を持つことが知られています。
この記事では、ヤマカガシの危険性と生態、そして遭遇したときの注意点について詳しく解説します。
ヤマカガシとは?
基本情報
- 和名:ヤマカガシ(山楝蛇)
- 学名:Rhabdophis tigrinus
- 分類:ナミヘビ科
- 分布:本州、四国、九州(一部地域を除く)、朝鮮半島、中国
体長は平均して 80cm〜120cm 程度。細長い体を持ち、色は地域や個体によって異なりますが、一般的には赤やオレンジの斑点と黒い模様が交じる鮮やかな見た目です。
ヤマカガシの毒と危険性
1. 首の後ろにある「毒腺」
ヤマカガシの最大の特徴は、首の後ろに毒腺を持っていることです。敵に襲われると、この部分から毒をにじませて防御します。実際には「毒をかける」ことはせず、噛まれた時や捕食者が飲み込んだ時に作用します。
2. 奥歯にある「出血毒」
さらにヤマカガシは、奥歯に毒牙を持つことが分かっています。この毒は「出血毒」で、血液を固まりにくくする作用があります。噛まれると血が止まりにくくなり、重症化すると脳出血や多臓器不全に至る危険性もあります。
3. 噛まれるリスクは低い?
ヤマカガシは本来おとなしい性格で、こちらから攻撃しない限り噛みついてくることはほとんどありません。また、毒牙が口の奥にあるため、浅く噛まれただけでは毒が注入されにくいとされています。
しかし、過去には重症例も報告されており、「危険性は低いが決して油断できない」毒蛇と言えるでしょう。
ヤマカガシの生態
1. 主な生息地
ヤマカガシは水辺を好みます。田んぼ、池、川、湿地、公園の水路などでよく見られます。人間の生活圏にも近いため、農作業中や子どもの川遊び中に遭遇することもあります。
2. 食性
主に カエル を捕食します。特にトノサマガエルやアマガエルをよく食べ、環境によっては魚や小さな哺乳類、昆虫も食べます。実はこのカエルの毒を体内に取り込み、自分の毒として利用していると考えられています。
3. 活動時期
- 春から秋にかけて活発
- 冬は冬眠し、落ち葉や土の中でじっとしています。
- 昼行性で日中に活動することが多いですが、気温が高い時期には夕方や夜に動くこともあります。
ヤマカガシとマムシの違い
日本でよく話題になる毒蛇「マムシ」とヤマカガシを比べてみましょう。
| 特徴 | ヤマカガシ | マムシ |
|---|---|---|
| 体長 | 80〜120cm | 45〜60cm(太く短い) |
| 模様 | 赤・黒の派手な斑点 | 茶色で地味な斑紋 |
| 毒の種類 | 出血毒 | 神経毒+出血毒 |
| 性格 | おとなしい | 攻撃的 |
| 危険度 | 低いが重症例あり | 高い(噛まれる事故が多い) |
マムシは攻撃的で人間を噛む事故も多いため、危険度はマムシの方が高いとされています。ただし、ヤマカガシも油断は禁物です。
ヤマカガシに遭遇したら?
もし野外でヤマカガシに出会ったら、以下の点に注意しましょう。
- むやみに近づかない
見つけても触らず、その場を離れることが最善です。 - 捕まえようとしない
子どもが遊び半分で触ろうとするのは非常に危険です。 - 噛まれたらすぐ病院へ
出血が止まらない場合は重症化の恐れがあります。迷わず救急搬送を。
まとめ|ヤマカガシは「知っていれば怖くない毒蛇」
- ヤマカガシは日本に広く分布する 身近な毒蛇。
- 毒は「首の毒腺」と「奥歯の出血毒」の2種類。
- おとなしい性格で、こちらから刺激しない限り危険は少ない。
- しかし過去には死亡例もあり、油断は禁物。
- 正しい知識を持ち、遭遇したら距離を取って安全を確保することが大切。
ヤマカガシは恐ろしい面を持ちながらも、生態系においてはカエルを捕食するなど重要な役割を果たしています。無闇に恐れるのではなく、「正しく知って共存する」ことが必要です。
この記事は個人で収集した情報をもとに記載していますので、誤った情報を記載している可能性があります。
この記事だけではなく、他の方が公開されている情報もぜひチェックしてみてください