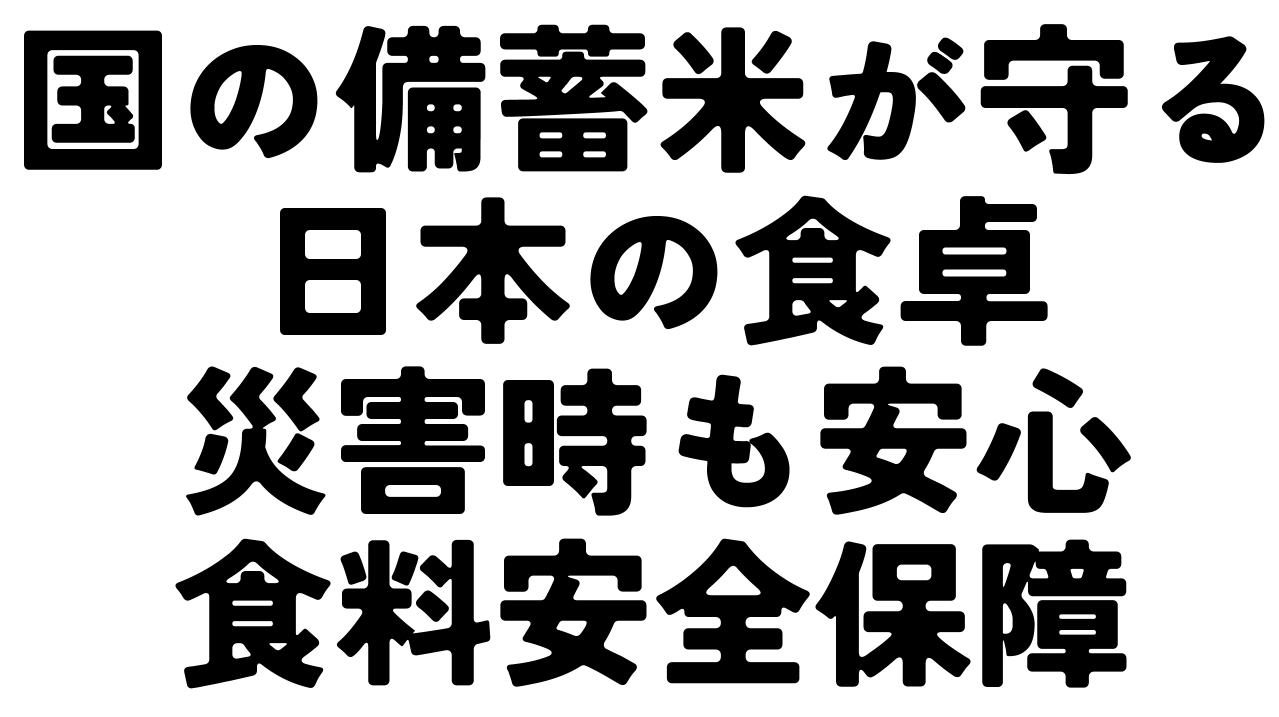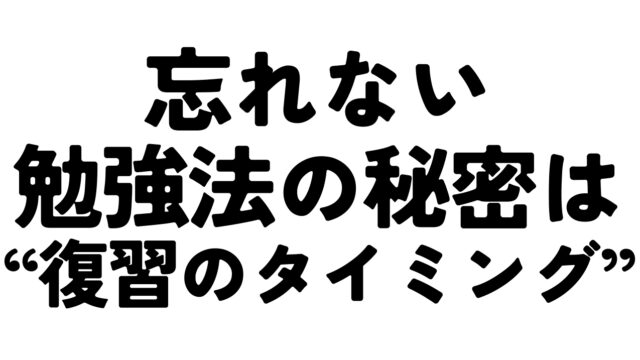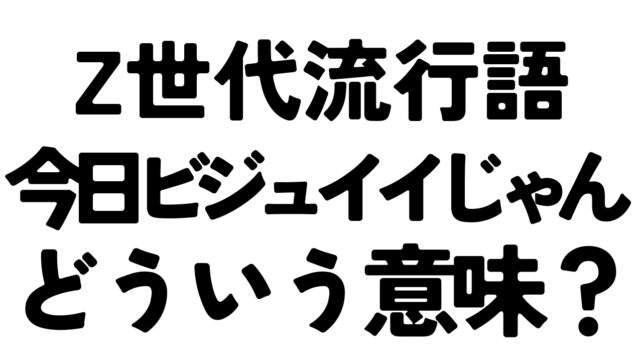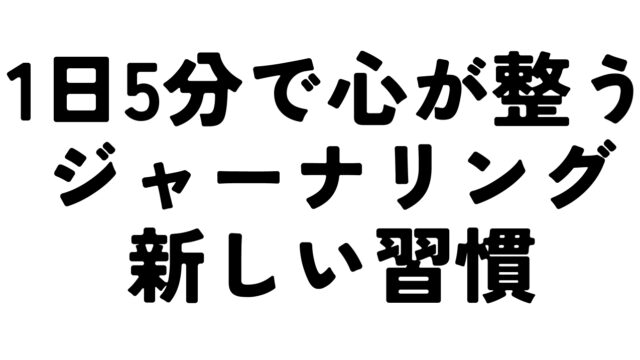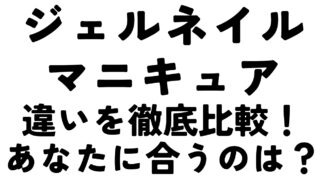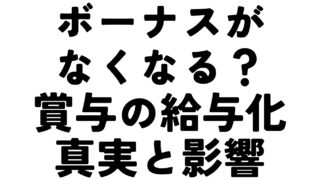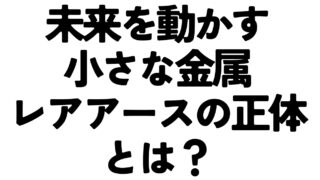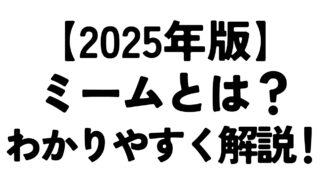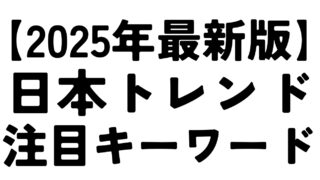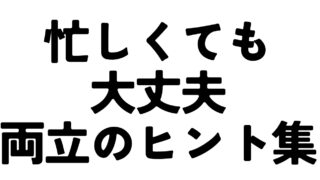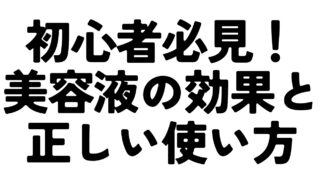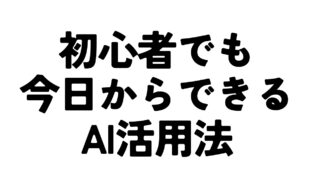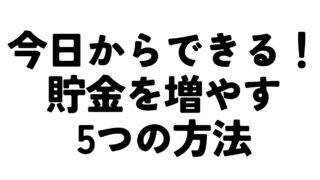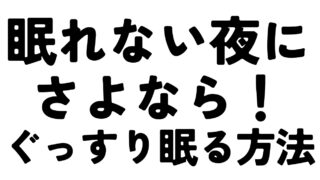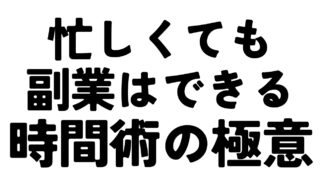「備蓄米」という言葉を聞くと、防災用や家庭での長期保存食を思い浮かべる方も多いでしょう。
しかし、実は国も大規模にお米を備蓄していることをご存じでしょうか?
それが「国の備蓄米(政府備蓄米)」です。
この制度は日本の食料安全保障を守るために導入され、私たちの暮らしを陰ながら支えています。
本記事では、国の備蓄米の目的・仕組み・役割をわかりやすく解説し、一般家庭での備蓄米との違いもまとめます。
国の備蓄米とは?
国の備蓄米とは、農林水産省が食料安全保障のために備蓄しているお米のことです。
正式には「政府備蓄米」と呼ばれ、主に国内産米が対象となります。
備蓄米は農家から買い入れられ、一定期間保存されたのち、用途に応じて放出されます。
その目的は「食料の安定供給」を確保することにあります。
国の備蓄米制度の目的
- 食料危機への備え
自然災害や不作、国際情勢による輸入停滞など、食料不足に備えるため。 - 米の需給と価格の安定
市場における米の供給量を調整し、価格が乱高下しないようにする。 - 災害時の緊急放出
大規模災害時には、被災地支援として米を供給する役割も担う。
つまり、国の備蓄米は「国民の食生活の安全網」として存在しているのです。
備蓄米はどのくらい保存されている?
政府は毎年約100万トン規模のお米を備蓄しています。
この量は、国民1人あたり約8kgに相当します。
保存期間は通常5年程度で、古くなった備蓄米は学校給食、加工食品、海外援助などに活用され、無駄なく循環する仕組みが整っています。
国の備蓄米の仕組み
1. 買い入れ
農家から主食用米を買い取り、政府が保管。
2. 保管
低温倉庫などで適切に保管され、品質を維持。
3. 放出
保存期間が近づいたものは市場や公共用途に放出。
このサイクルを繰り返すことで、備蓄米は常に新しい状態が保たれています。
国の備蓄米の活用例
- 学校給食用米
一定期間を過ぎた備蓄米が教育現場で提供されます。 - 加工用米
おせんべいや米菓、日本酒などの原料に利用。 - 国際援助(食糧支援)
飢餓や自然災害に苦しむ国への支援として提供されることもあります。
こうした流れで、備蓄米は「ただ保管するだけ」でなく、循環して活用されているのです。
国の備蓄米と家庭用備蓄米の違い
| 項目 | 国の備蓄米 | 家庭の備蓄米 |
|---|---|---|
| 保存量 | 約100万トン規模 | 家族単位(数kg〜数十kg) |
| 保存目的 | 食料安全保障、価格安定、災害支援 | 災害時の食事確保、日常利用 |
| 保存方法 | 大型低温倉庫、厳格な管理 | 真空パック米、アルファ化米、レトルト米など |
| 活用方法 | 学校給食、加工用、海外援助 | 非常食、日常ご飯、アウトドア |
両者は規模も目的も異なりますが、共通しているのは「私たちの食を守る」役割です。
国の備蓄米があることの安心感
- 日本は食料自給率が低いため、国の備蓄は非常時の命綱
- 天候不順や国際紛争など、予測できないリスクにも対応可能
- 子どもたちの学校給食や国際援助にも役立つ
つまり、国の備蓄米は「国民の命と暮らしを守るための食料保険」と言えるのです。
まとめ|国の備蓄米は日本の食を守る重要な制度
- 国の備蓄米(政府備蓄米)は、農家から買い入れられ、数年間保存されたのちに循環活用される
- 食料危機への備え、市場安定、災害支援など多様な役割を持つ
- 学校給食や国際援助にも活用され、社会に貢献している
- 家庭の備蓄米と役割は違うが、どちらも「食の安心」を支える存在
私たちが普段口にするご飯の裏には、こうした国家的な備蓄制度があることを知っておくと、日々の食のありがたみを実感できるのではないでしょうか。
この記事は個人で収集した情報をもとに記載していますので、誤った情報を記載している可能性があります。
この記事だけではなく、他の方が公開されている情報もぜひチェックしてみてください