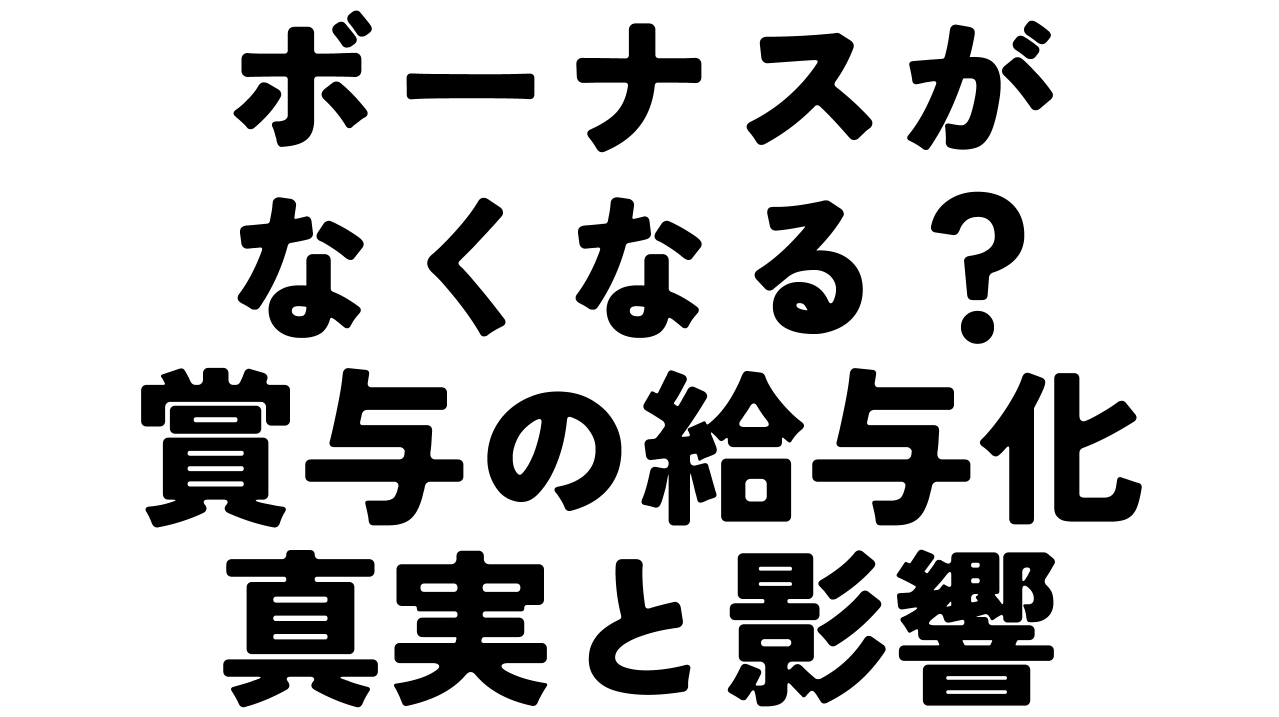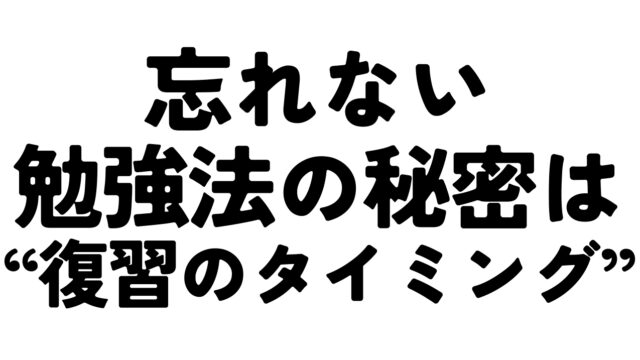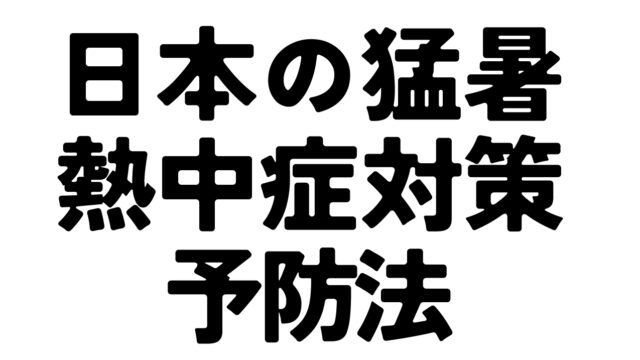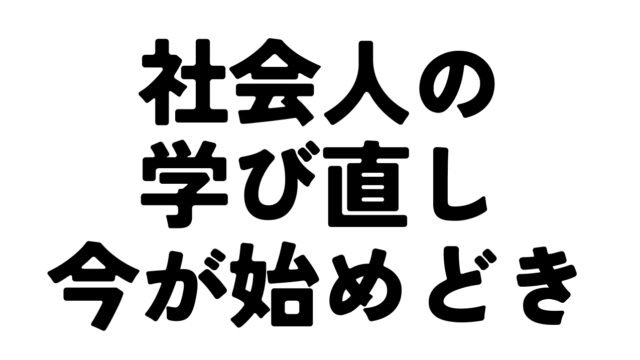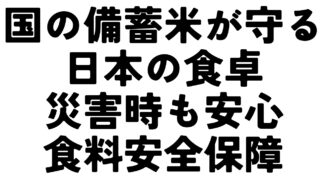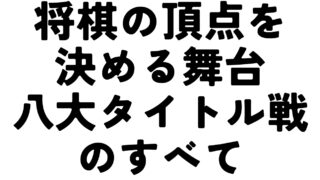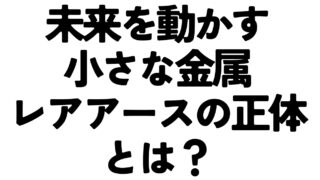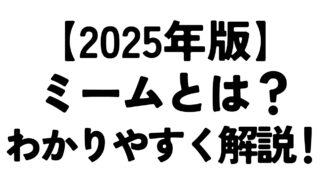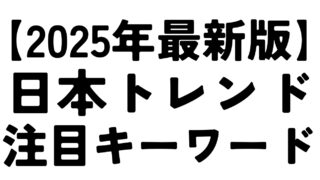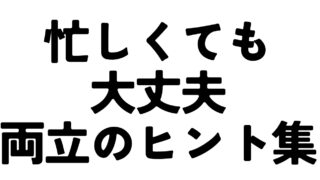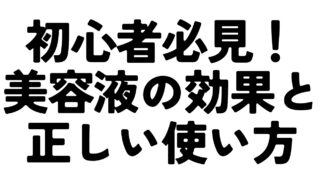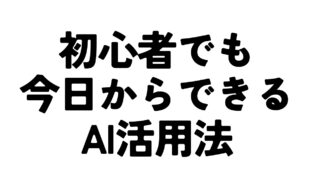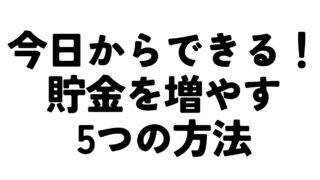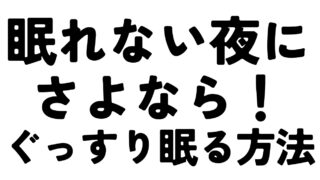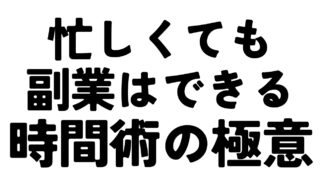日本の給与制度には「月給(基本給)」と「賞与(ボーナス)」があります。
一般的に、賞与は年に1〜2回支給され、会社の業績や個人の評価によって金額が変動する仕組みです。
ところが近年、一部の企業では「賞与を給与に組み込む=賞与の給与化」という動きが見られます。
では、なぜ賞与を給与化する企業があるのでしょうか?
本記事では、その理由や背景、従業員への影響についてわかりやすく解説します。
賞与の給与化とは?
「賞与の給与化」とは、従来ボーナスとして支給されていた金額を毎月の給与に分割して支給する仕組みです。
例えば、
- 従来:月給25万円+年2回の賞与50万円
- 給与化後:月給29万円(賞与分を毎月に上乗せ)、賞与はなし
このように、賞与を廃止して毎月の給与に含める形になります。
企業が賞与を給与化する理由
1. 人件費の安定化
賞与は業績に左右されるため、企業にとっては支出が変動しやすいものです。
給与化することで、毎月の人件費を一定に保ち、経営計画を立てやすくなります。
2. 雇用の安定をアピール
「ボーナスが出ない年がある」よりも「毎月の給与が安定している」方が従業員に安心感を与える場合があります。
特に若手社員やローンを抱える人にとっては月収が高い方が生活設計が立てやすいのです。
3. 雇用流動化・成果主義の影響
近年は終身雇用の考え方が薄れ、成果主義が重視される傾向にあります。
賞与を給与化することで、「業績連動のボーナス」から「成果に応じた給与」へと移行しやすくなるのです。
4. 社会保険料の調整
賞与も社会保険料の対象ですが、給与に含めると標準報酬月額の範囲で安定的に保険料を徴収できるため、事務処理の効率化につながります。
賞与の給与化によるメリット
従業員にとってのメリット
- 毎月の手取りが増える
生活費や住宅ローンの返済計画を立てやすい。 - ボーナスが減る不安がない
業績に左右されず、安定した収入が得られる。 - 転職市場での収入比較がしやすい
月収が高く見えるため、求人比較時に有利になる場合も。
企業にとってのメリット
- 人件費の予測がしやすい
賞与分の変動が減り、経営計画を立てやすい。 - 雇用の安定感をアピールできる
「毎月の給与が高い企業」として人材確保につながる。 - 社会保険料の計算がシンプルになる
賞与の給与化によるデメリット
従業員にとってのデメリット
- 賞与の楽しみがなくなる
まとまった金額が入る喜びや旅行・買い物の資金が得にくくなる。 - 税制上の損失が出る可能性
賞与には特別な税率計算があり、場合によっては給与化により手取りが減ることも。 - モチベーション低下の懸念
業績や個人の成果が給与に反映されにくくなる。
企業にとってのデメリット
- 賞与による業績連動型のインセンティブを失う
社員にとって「頑張ればボーナスで還元される」というモチベーションが弱まる。 - 従業員からの不満リスク
「ボーナスがない=やる気が出ない」と思う社員も一定数いる。 - 求人市場で不利になる可能性
「賞与なし」と書かれると、求職者にネガティブな印象を与える場合がある。
賞与の給与化は違法ではないの?
結論から言えば、賞与を給与化すること自体は違法ではありません。
ただし、以下の条件を満たす必要があります。
- 就業規則や労働契約に基づいて制度を変更すること
- 労使協定や従業員への十分な説明があること
- 労働基準法に定める賃金支払いの5原則を守ること
つまり、正しい手続きを踏めば企業は自由に制度設計できるのです。
賞与の給与化に関するよくある疑問
Q1. 手取りは増えるの?減るの?
ケースによります。
給与化で毎月の手取りは増えますが、社会保険料や税金が上がることで結果的に賞与時より負担が大きくなる場合もあります。
Q2. 転職に不利になる?
企業によっては「賞与あり」の方が魅力的に映りますが、月収が安定して高いことはメリットでもあります。
ただし求人票では「賞与なし」と記載されるため、応募者に誤解を与える可能性はあります。
Q3. 今後は賞与の給与化が増えるの?
人件費の固定化を好む企業や、成果主義を重視する業界では増える傾向にあります。
ただし日本の文化的に「ボーナスを楽しみにする」人も多いため、完全に主流になる可能性は低いでしょう。
まとめ|賞与の給与化は「安定」と「やりがい」のバランスが重要
- 賞与の給与化は、企業の人件費安定化や従業員への安定収入の提供を目的として導入される
- メリットは「毎月の収入が増える」「安定性が高い」こと
- デメリットは「ボーナスの楽しみがなくなる」「モチベーションが下がる可能性」など
- 違法ではないが、労働契約や説明責任を果たす必要がある
従業員にとっては「安定した生活を送れるか」「やる気を保てるか」が重要なポイントです。
企業にとっても、人材確保やモチベーション維持の観点から、慎重な判断が求められます。
この記事は個人で収集した情報をもとに記載していますので、誤った情報を記載している可能性があります。
この記事だけではなく、他の方が公開されている情報もぜひチェックしてみてください