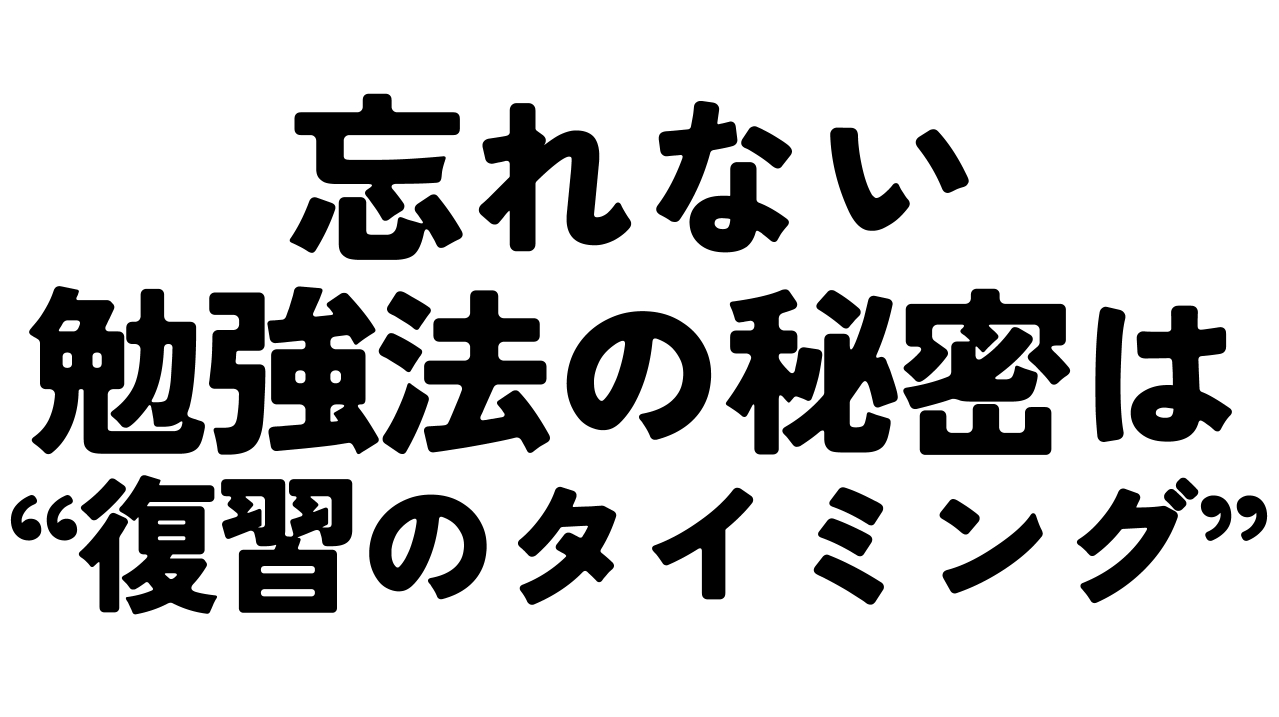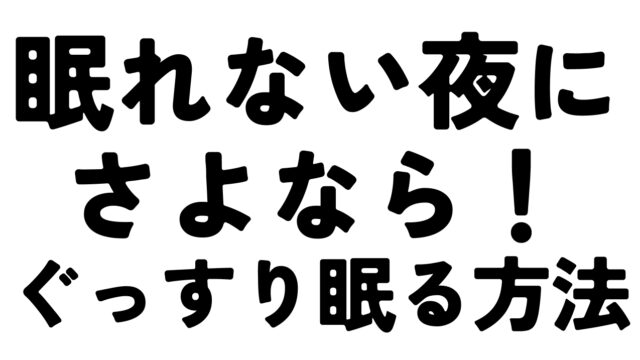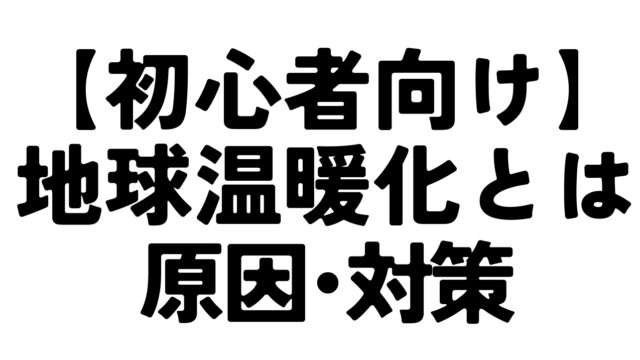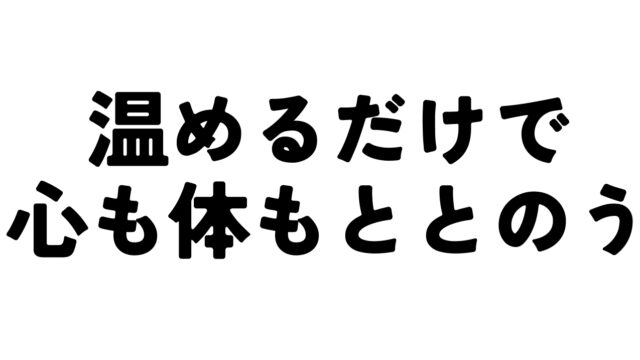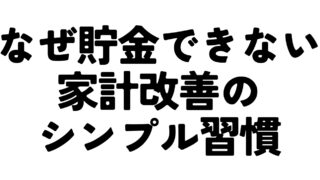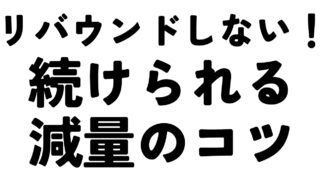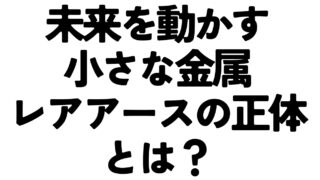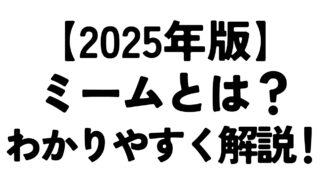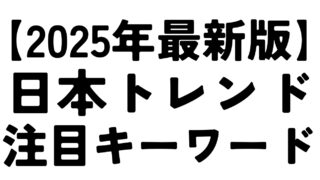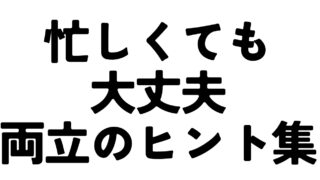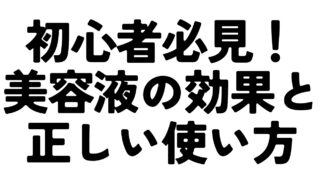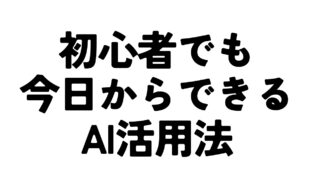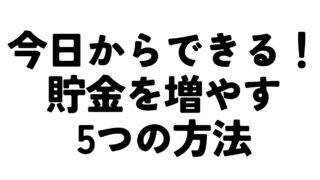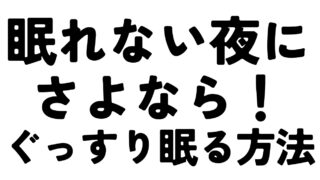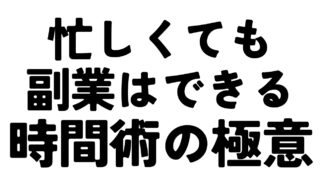「テスト前に一生懸命勉強したのに、すぐに忘れてしまう…」
「暗記に時間をかけても頭に残らない…」
多くの人が抱えるこの悩みには、実は脳の記憶の仕組みが深く関わっています。忘れてしまうのは「自分の頭が悪いから」ではなく、脳の働きに沿った学び方をしていないからなのです。
本記事では、記憶の仕組み、忘れる理由、効率的に記憶を定着させる勉強法や復習のタイミング、役立つ学習ツール について詳しく解説します。
記憶の仕組みを理解しよう
1. 記憶の3段階プロセス
人間の記憶は、大きく分けて3つのプロセスで成り立っています。
- 記銘(インプット):情報を頭に入れる段階
- 保持(ストレージ):情報を一時的・長期的に保存する段階
- 想起(アウトプット):必要な時に情報を取り出す段階
どこかの段階でうまく機能しないと、勉強しても記憶に残らなかったり、思い出せなくなってしまいます。
2. 短期記憶と長期記憶
- 短期記憶:数秒〜数分程度しか保持できない。一時的なメモのようなもの。
- 長期記憶:繰り返し使うことで、脳に強固に保存される情報。
勉強内容を「長期記憶」に移行させることが、忘れないための鍵です。
なぜ忘れてしまうのか?
1. エビングハウスの忘却曲線
ドイツの心理学者エビングハウスによる実験では、人は学んだことの約半分を1日以内に忘れることが分かっています。つまり「復習しない勉強」は、ほとんど意味がないのです。
2. アウトプット不足
読むだけ・聞くだけの勉強では、記憶が浅くなりやすいです。人間の脳は「思い出す」ことで情報を強く定着させます。
3. 睡眠不足
睡眠中に脳は記憶を整理し、長期記憶へと移行させます。睡眠不足は、せっかく勉強した内容を脳に定着させるチャンスを奪ってしまいます。
4. 集中力の低下
長時間ダラダラ勉強しても、記憶効率は下がります。脳は集中できる時間に限りがあるため、休憩を挟みながら短時間で集中する方が効果的です。
効率的に記憶を定着させる勉強法
1. 分散学習(スパイシング効果)
一度に長時間勉強するより、短時間を複数回に分けて勉強する方が記憶に残ります。
例:1日3時間を一気に勉強するのではなく、1時間×3回に分ける。
2. 復習のタイミング(反復学習)
忘却曲線に沿って復習することが効果的です。
- 学習後24時間以内に1回復習
- 1週間以内に2回目の復習
- 1か月後に3回目の復習
このサイクルを守ると、長期記憶に移行しやすくなります。
3. アウトプット学習
- 問題集を解く
- 人に説明する
- ノートを見ずに要点を書き出す
「思い出そうとする行為」こそが、記憶を強化する最大の方法です。
4. アクティブ・ラーニングを取り入れる
ただ読むだけでなく、手を動かす・声に出す・図解するなど、複数の感覚を使うことで記憶が定着します。
5. 睡眠と運動を意識する
- 睡眠:勉強後の十分な睡眠が記憶の固定に不可欠。
- 運動:軽い運動は脳の血流を促し、記憶力を高めます。
効率的に学習をサポートするツール
1. フラッシュカードアプリ
「Anki」「Quizlet」などを使えば、忘却曲線に沿った復習が自動化できます。
2. タイマー学習(ポモドーロ・テクニック)
25分勉強+5分休憩を繰り返すことで、集中力を維持できます。
3. マインドマップ
情報を図解して整理することで、理解と記憶が深まります。
4. 音声学習ツール
移動時間や隙間時間に、音声で復習するのも効果的です。
今日からできる!忘れない勉強法チェックリスト
- □ 勉強したら24時間以内に復習する
- □ 問題を解いてアウトプットを増やす
- □ まとめノートを自分の言葉で書く
- □ 勉強後はしっかり睡眠をとる
- □ 学習アプリやタイマーで効率化する
まとめ
勉強しても忘れてしまうのは、脳の仕組みに沿っていない学び方をしているからです。
「復習のタイミング」「アウトプット」「睡眠と生活習慣」を意識すれば、記憶は格段に定着しやすくなります。
今日から、短時間の分散学習と復習のサイクルを取り入れてみましょう。きっと「忘れない勉強」が実感できるはずです。
この記事は個人で収集した情報をもとに記載していますので、誤った情報を記載している可能性があります。
この記事だけではなく、他の方が公開されている情報もぜひチェックしてみてください