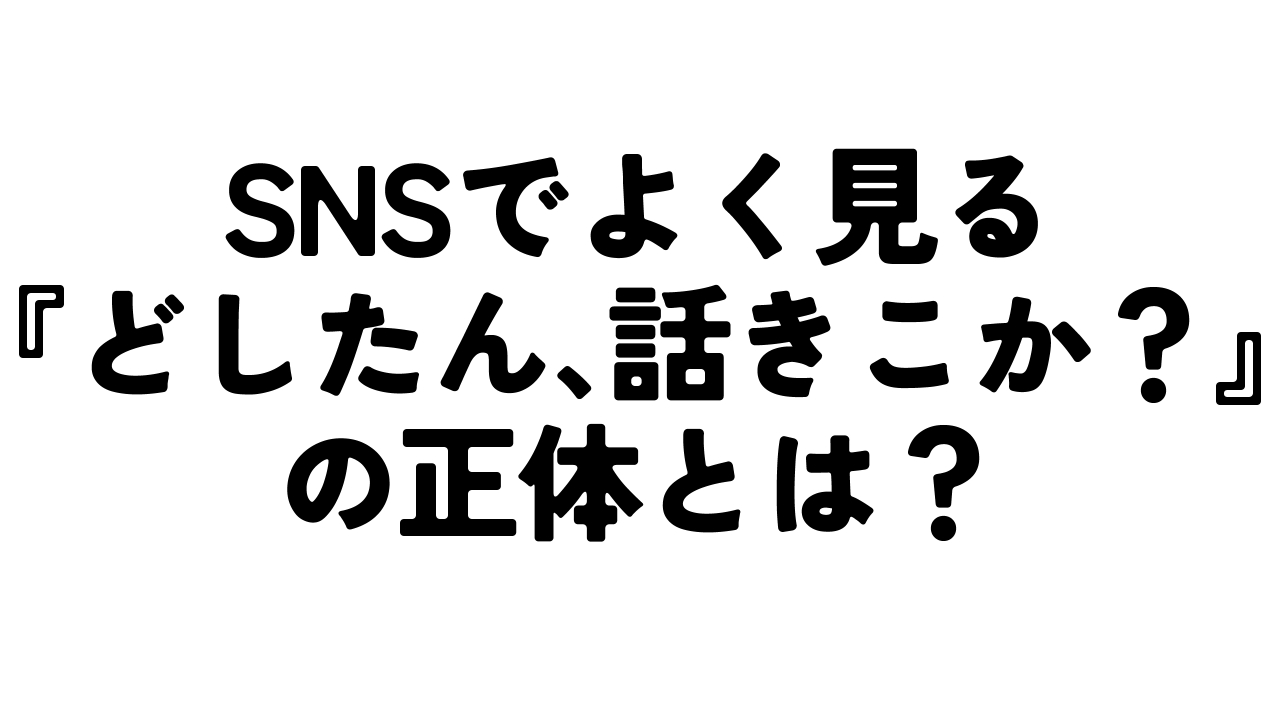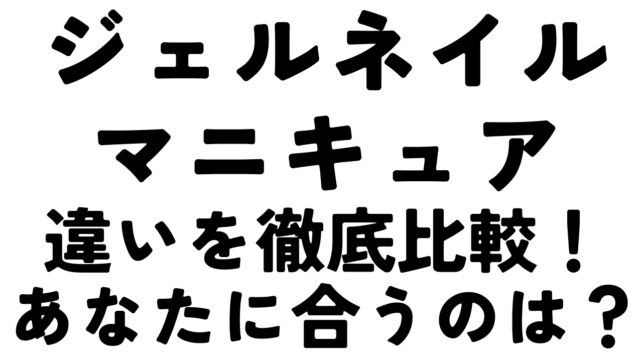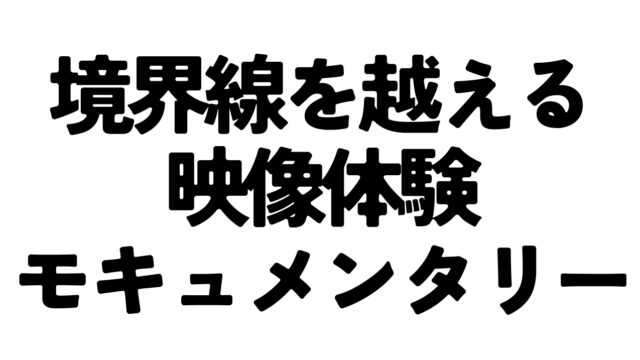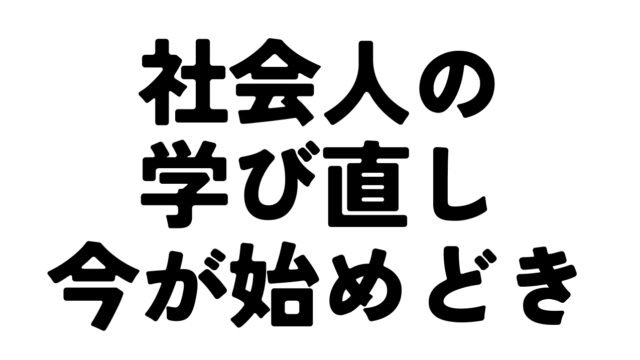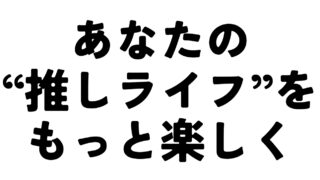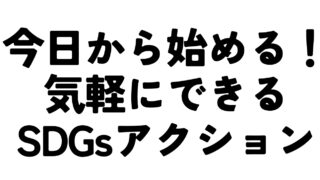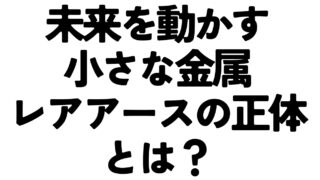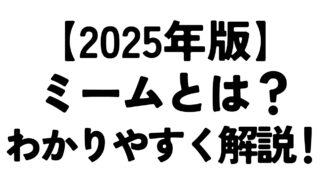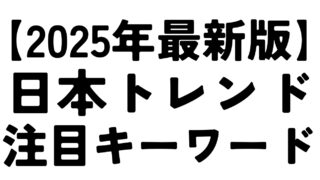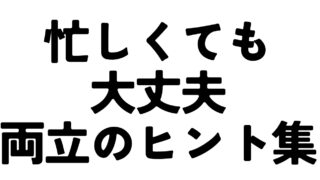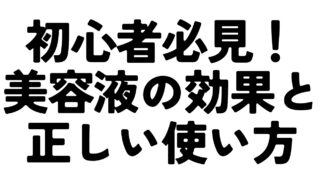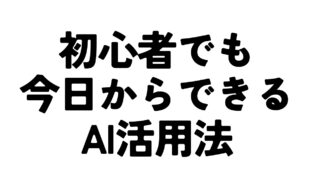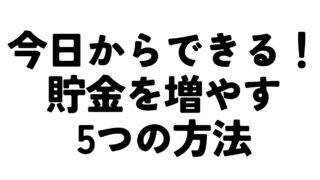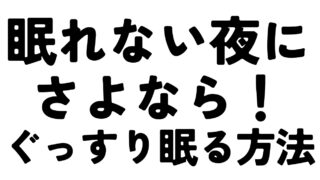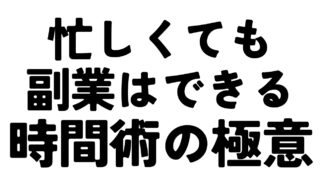SNSやネット掲示板を利用していると、ふと目にする独特なフレーズがあります。そのひとつが 「どしたん、話きこか?」 です。関西弁風の口調で書かれるこの一言は、どこか親しみやすく、同時にユーモラスな響きを持っています。
では、このフレーズはどのように誕生し、どんな場面で使われるようになったのでしょうか? 本記事では「どしたん、話きこか?」の由来や意味、SNSでの使い道、注意点までを解説します。
「どしたん、話きこか?」とは?
「どしたん、話きこか?」を直訳すると「どうしたの?話聞こうか?」となります。つまり、相手の困りごとや悩みに対して、「私でよければ話を聞くよ」と声をかけるフレーズです。
しかし、ネット上で使われる場合には必ずしも“本気で心配している”ニュアンスだけではありません。どちらかといえば、ちょっとした愚痴や不満、構ってほしそうな投稿に対して軽くツッコむような意味合いで用いられることが多いのです。
誕生の背景:ネット掲示板から広がったフレーズ
この言葉の起源は、主にネット掲示板文化やSNSでのユーザー同士のやり取りからといわれています。
例えばTwitter(現X)や5ちゃんねるでは、誰かが長文で愚痴をこぼしたり、「つらい…」など意味深な投稿をしたときに、他のユーザーが「どしたん、話きこか?」と軽くコメントすることで場を和ませるパターンが多く見られます。
関西弁風の親しみやすさ
標準語で「どうしたの?話聞こうか?」と書くと少し堅苦しい印象になりますが、関西弁風に「どしたん」と崩すことで柔らかさやユーモアが増します。これがネットミームとして広まった理由のひとつと考えられます。
使い道①:SNSでの軽いツッコミ
もっとも多いのはSNSでのリアクションとしての使い方です。
- 「もう人生疲れた…」と書く友人の投稿に → 「どしたん、話きこか?」
- 「推しが尊すぎて泣いてる」 → 「どしたん、話きこか?」
- 「上司に怒られた…」 → 「どしたん、話きこか?」
このように、深刻さとユーモアのバランスを取りながらコメントすることで、相手を和ませつつ会話のきっかけを作るのに役立ちます。
使い道②:ネタとしての自虐・セルフツッコミ
「どしたん、話きこか?」は他人へのツッコミだけでなく、自分自身に対して使うケースもあります。
- 自分で意味深なツイートをしたあとに「どしたん、話きこか?(自分)」とセルフ返信する
- 愚痴っぽい日記を投稿したあとに「誰か『どしたん、話きこか?』って言って」などと書く
このように、ネタとして自己完結する形でも人気があります。
使い道③:スタンプ・画像・ミーム
近年はLINEスタンプやTwitterの画像ミームでも「どしたん、話きこか?」が多用されています。
- イラストに吹き出しで「どしたん、話きこか?」と入れる
- ペットやキャラクターの写真と組み合わせて投稿する
こうしたビジュアル化によって、一層ユーモラスに使えるようになり、幅広い層に定着しました。
「どしたん、話きこか?」が人気になった理由
- 関西弁の柔らかさ
フランクで親しみやすい響きが、SNSに適していた。 - 万能性
悩み相談からオタク的な喜びまで、幅広い投稿に対応可能。 - ユーモア性
深刻になりすぎず、場を和ませる効果がある。 - 拡散力
スタンプや画像との相性が良く、ネットミームとして広まりやすかった。
注意点:使うときのマナー
ただし、「どしたん、話きこか?」は万能ではありません。使い方を間違えると失礼に受け取られることもあります。
- 本当に深刻な悩みを抱えている人に軽く使わない
- 冗談が通じない相手には控える
- オンラインとオフラインでは温度感が違う
相手との距離感を意識して使うことが大切です。
まとめ:軽さとユーモアでつながる「どしたん、話きこか?」
「どしたん、話きこか?」は、関西弁風のフランクさが魅力のネットスラングです。SNSを中心に広まり、愚痴やネガティブな投稿に対して軽いツッコミとして使われています。
ただし本気で悩んでいる人に対しては軽率に使わず、ユーモアが通じる場面で利用することがポイントです。
ネット文化が生み出した言葉遊びの一例として、「どしたん、話きこか?」は今後もしばらく多くの場面で見かけることになるでしょう。
この記事は個人で収集した情報をもとに記載していますので、誤った情報を記載している可能性があります。
この記事だけではなく、他の方が公開されている情報もぜひチェックしてみてください