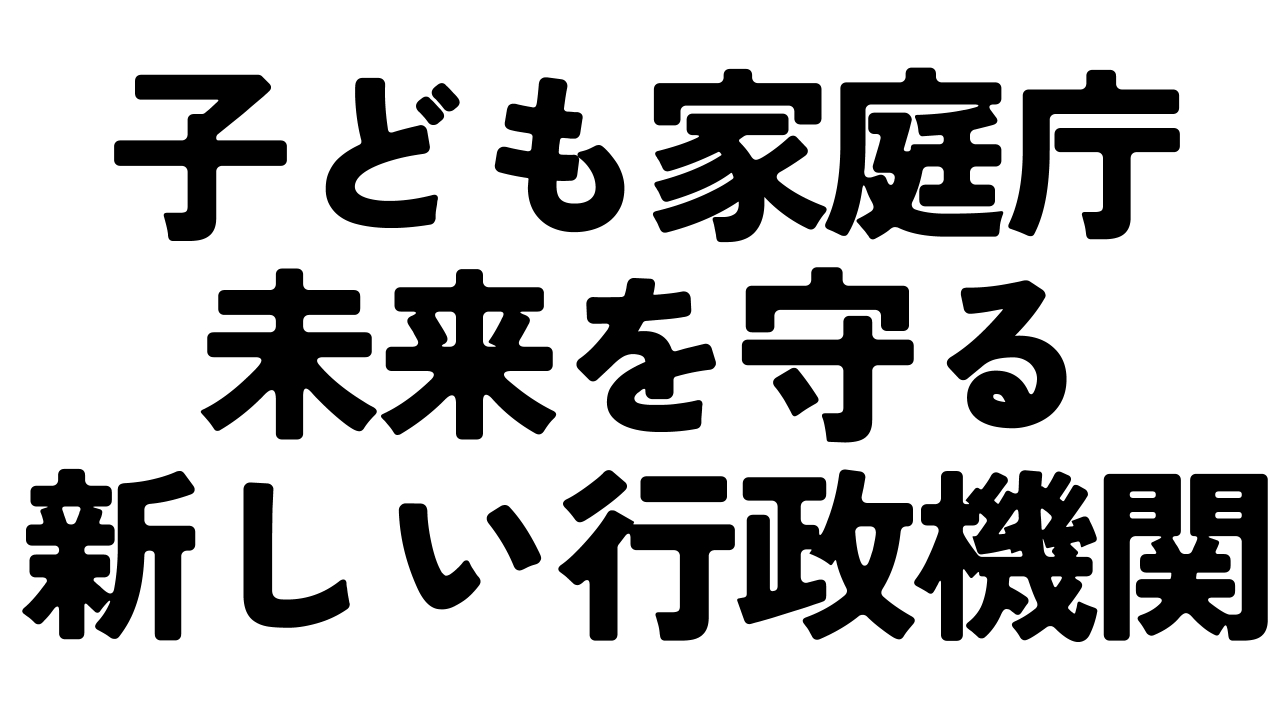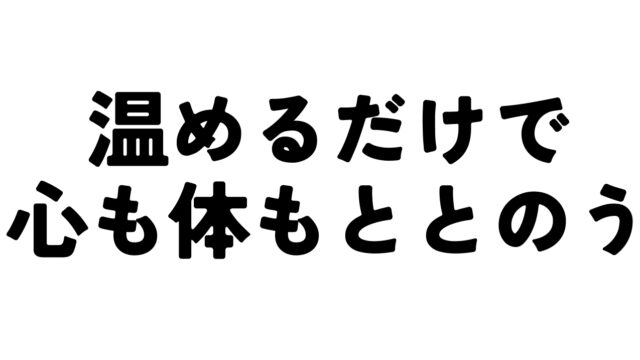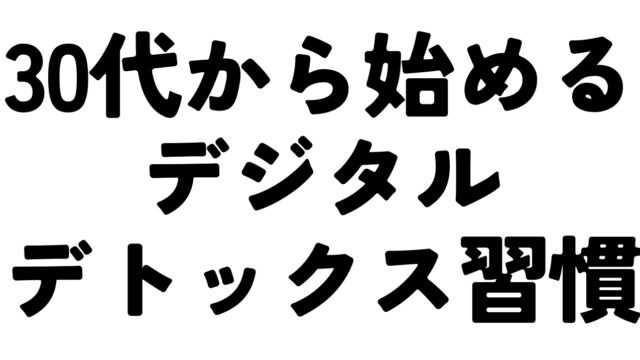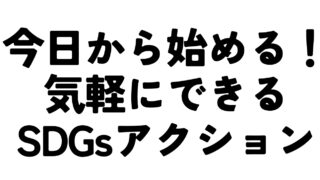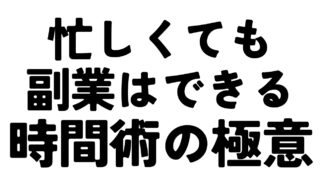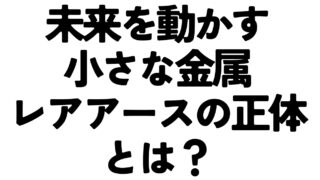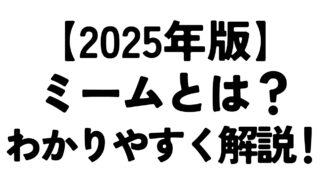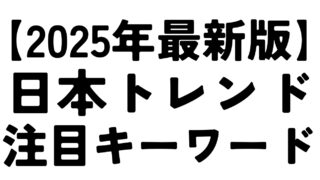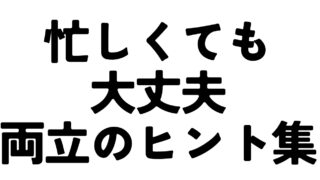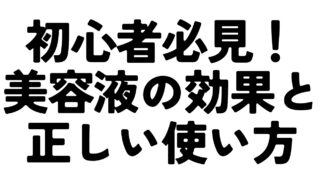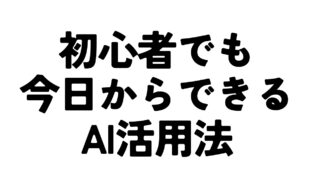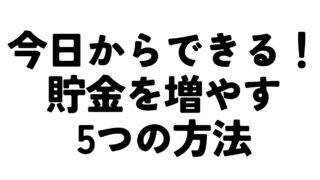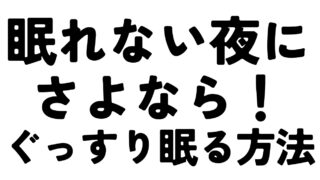2023年4月、日本に新しく「子ども家庭庁」という行政機関が誕生しました。
ニュースなどで耳にする機会が増えましたが、「どんなことをしているの?」「厚生労働省や文部科学省と何が違うの?」と疑問を持つ人も少なくありません。
この記事では、子ども家庭庁の目的や役割、具体的な取り組み内容をわかりやすくまとめます。子育て世代だけでなく、社会全体に関わるテーマなので、知っておくと役立ちます。
子ども家庭庁が設立された背景
日本は今、少子化・人口減少という大きな課題に直面しています。出生数は年々減少し、2022年にはついに80万人を割り込みました。
また、子どもの貧困やいじめ、虐待、ヤングケアラー(家族の介護を担う子ども)など、社会の中で子どもや家庭が抱える問題も複雑化しています。
従来、子どもに関する政策は厚生労働省・文部科学省・内閣府など複数の省庁に分かれて担当していました。しかし、縦割り行政の弊害により十分な連携がとれず、支援が遅れるケースも少なくありませんでした。
そこで、子どもや家庭に関する政策を一元化して推進するために設立されたのが「子ども家庭庁」です。
子ども家庭庁の基本理念
子ども家庭庁の基本理念は、次の3つにまとめられます。
- 子どもの最善の利益を第一に考える
子どもの権利条約に基づき、子どもの意見や視点を尊重する。 - 子ども・若者の声を政策に反映する
実際に子どもや若者の意見を聞き、施策に取り入れる仕組みを作る。 - 関係機関の連携を強化する
学校、地域、福祉機関などがスムーズに連携できるようにする。
子ども家庭庁の主な役割と取り組み
それでは具体的に、子ども家庭庁が担っている役割を見ていきましょう。
1. 子どもの貧困対策
日本では子どもの7人に1人が相対的貧困状態にあるといわれています。
子ども家庭庁は、学習支援や生活支援、給付金制度の整備などを進めています。特にひとり親家庭への支援や就学援助制度の改善など、教育格差をなくす取り組みが進められています。
2. 虐待防止と子どもの安全確保
児童虐待の相談件数は年々増加しています。子ども家庭庁は、
- 児童相談所の強化
- 通報・相談体制の拡充
- SNSを活用した相談窓口の設置
などを行い、子どもの命を守る仕組みを強化しています。
3. 教育・発達支援
文部科学省との連携を取りながら、発達障害や学習障害を持つ子どもへのサポート、放課後児童クラブや学童保育の拡充を進めています。
また、ヤングケアラーの支援体制も整備し、子どもが「学び」と「生活」の両立をしやすい環境を目指しています。
4. 少子化対策・子育て支援
子ども家庭庁の大きな柱が少子化対策です。具体的には:
- 出産育児一時金の引き上げ
- 育児休業の取得促進
- 保育サービスや待機児童問題の解消
- 経済的支援の充実
こうした施策を通じて、「子どもを産み育てやすい社会」の実現を目指しています。
5. 子どもの声を聞く仕組み
子ども家庭庁は「子ども・若者参画チーム」を設置し、実際に子どもや若者の意見をヒアリングしています。アンケート調査やオンライン対話イベントを通じて、子どもの声が政策に反映される仕組みづくりを進めているのが大きな特徴です。
子ども家庭庁が重視する「子どもの権利」
設立にあたって特に強調されているのが、「子どもの権利」を守ることです。これは国連の子どもの権利条約に基づき、次のような権利を保障するものです。
- 生きる権利
- 守られる権利(虐待や差別から守られる)
- 育つ権利(教育や医療を受ける)
- 参加する権利(意見を表明する)
日本ではこれまで十分に浸透していなかった考え方ですが、子ども家庭庁の活動を通じて、社会全体に広がりつつあります。
子ども家庭庁の課題と今後の展望
もちろん、子ども家庭庁には課題もあります。
- 行政組織としての歴史が浅く、まだ調整に時間がかかる
- 各自治体での支援体制に差がある
- 予算や人員の不足
しかし、設立されたばかりだからこそ柔軟に新しい仕組みを取り入れられるという強みもあります。今後は、デジタル技術の活用や、地域と家庭をつなぐネットワークづくりが期待されています。
まとめ:子どもと家庭を社会全体で支えるために
子ども家庭庁は、
- 子どもの貧困や虐待への対応
- 教育・発達支援
- 少子化対策と子育て支援
- 子どもの権利を守る仕組みづくり
といった幅広い役割を担っています。
「子育ては家庭だけの問題」ではなく、社会全体で子どもを支えるという意識が今まさに求められています。子ども家庭庁の活動を知ることは、子どもたちの未来を考える第一歩につながるでしょう。
この記事は個人で収集した情報をもとに記載していますので、誤った情報を記載している可能性があります。
この記事だけではなく、他の方が公開されている情報もぜひチェックしてみてください