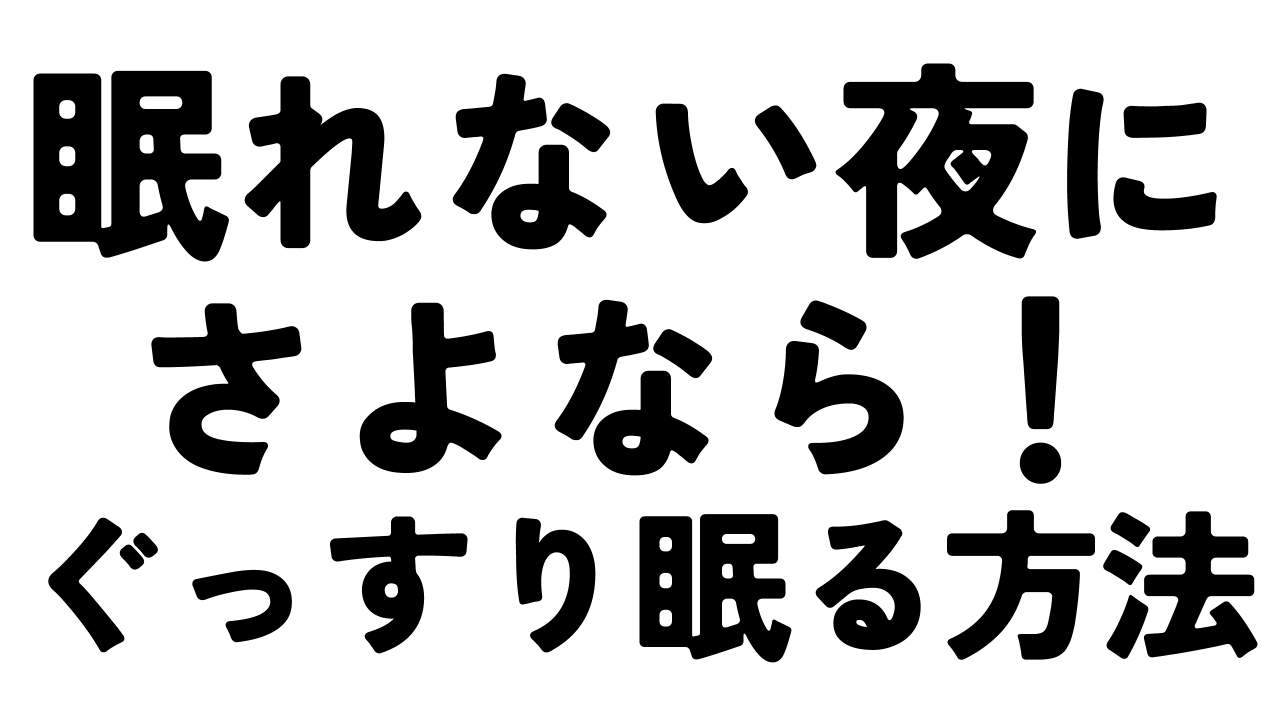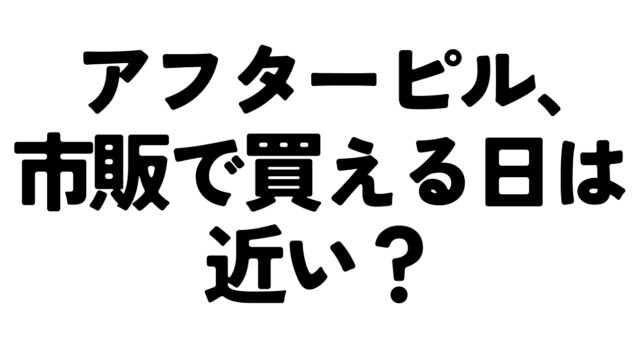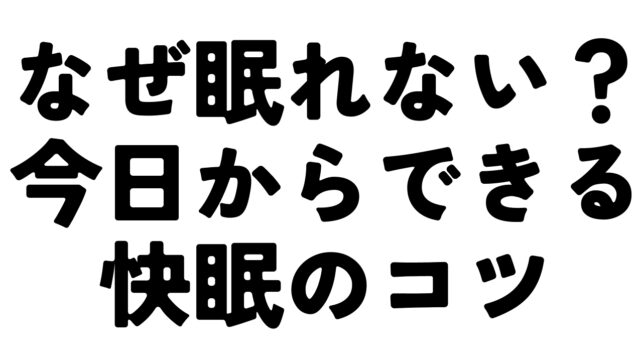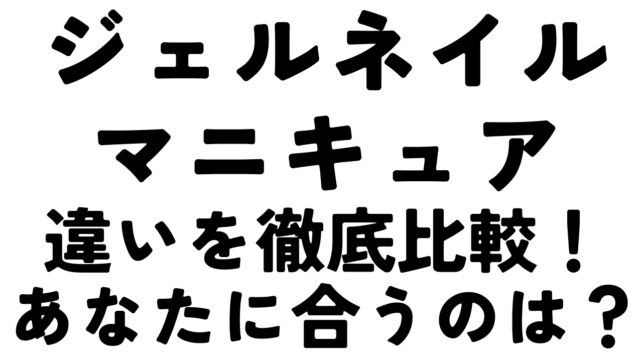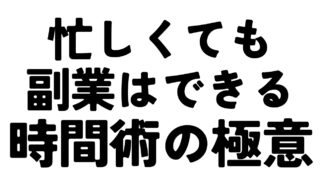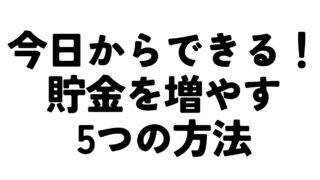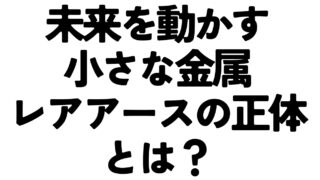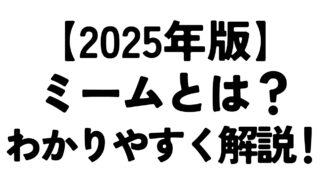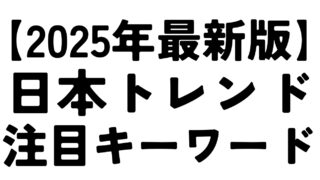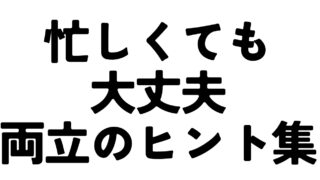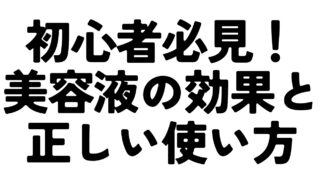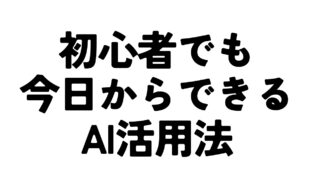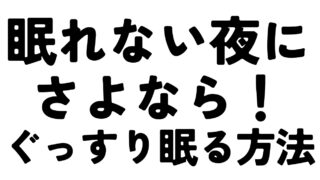現代社会で多くの人が抱える悩みのひとつに、「夜眠れない」「寝ても疲れが取れない」といった不眠があります。仕事や家庭、スマートフォンやパソコンの使用など、原因はさまざまです。眠れない状態を放置してしまうと、体調不良や集中力低下、心の不調、さらには免疫力の低下につながることもあります。
この記事では、不眠の原因を科学的に解説し、今日から実践できるぐっすり眠る方法を詳しく紹介します。
不眠とは?種類と症状
まず不眠の定義を押さえておきましょう。一般的に、不眠には以下のような症状があります。
- 寝つきが悪い(入眠困難)
- 夜中に何度も目が覚める(中途覚醒)
- 早朝に目が覚めてしまう(早朝覚醒)
- 十分な睡眠時間をとっても疲れが取れない(熟眠障害)
これらが週に3回以上、3か月以上続く場合、「慢性不眠症」と診断されることがあります。
不眠の主な原因
1. 自律神経の乱れ
自律神経は交感神経(活動モード)と副交感神経(休息モード)から成り、日中は交感神経、夜は副交感神経が優位になることで自然に眠くなります。しかし、ストレスや生活習慣の乱れで交感神経が優位な状態が続くと、体が休息モードに切り替わらず、不眠を招きます。
2. 生活習慣の乱れ
- 就寝・起床時間が不規則
- 夜遅くまでスマホやパソコンを操作
- カフェインやアルコールの摂取
これらは体内時計を狂わせ、眠りの質を低下させます。特にスマホやPCのブルーライトはメラトニン(睡眠ホルモン)の分泌を抑制し、寝つきが悪くなります。
3. ストレスや心理的要因
仕事や人間関係の悩み、将来への不安など心理的ストレスは、不眠の大きな原因です。夜になると脳が興奮状態にあり、眠ろうとしても頭が冴えてしまいます。
4. 食事や栄養の影響
消化に負担のかかる食事や脂っこい夜食、寝る直前のカフェイン摂取は睡眠を妨げます。また、栄養不足や偏った食生活は、睡眠ホルモンの分泌や自律神経のバランスに影響します。
5. 環境要因
- 騒音や光、温度・湿度の不適切
- 寝具の硬さや枕の高さ
こうした環境的な要因も、入眠を妨げることがあります。
ぐっすり眠るための具体的な方法
1. 睡眠環境を整える
- 室温は18〜22℃、湿度50〜60%
- 遮光カーテンで光を遮る
- 静かな環境を作る(耳栓やホワイトノイズ)
- 枕やマットレスの硬さを調整
睡眠環境を整えることは、質の高い眠りを確保する第一歩です。
2. 就寝・起床リズムを固定する
毎日同じ時間に寝て同じ時間に起きることで体内時計が整い、自然に眠くなるサイクルを作れます。休日の寝過ぎも避けましょう。
3. 食事と飲み物の工夫
- カフェインは午後以降控える
- 寝る3時間前には食事を終える
- 消化のよい軽めの夕食
- 温かい飲み物でリラックス(カモミールティーなど)
4. 適度な運動
- 朝や昼にウォーキング、ストレッチなど軽い運動
- 夜の激しい運動は避ける
運動は体温を上げ、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を促進します。
5. デジタルデトックス
- 就寝1時間前にはスマホ・PCを使わない
- ブルーライトカットの眼鏡やアプリを活用
- SNSの情報過多を避ける
6. ストレスケア・メンタルケア
- 日記やジャーナリングで悩みを書き出す
- 深呼吸や瞑想で心を落ち着ける
- 簡単なリラックス法(温かいお風呂、軽いストレッチ)を取り入れる
睡眠改善に役立つ補助法
- サプリやハーブ:メラトニン、ラベンダー、カモミール
- 光療法:朝の太陽光で体内時計をリセット
- 寝る前のルーティン:同じ行動(歯磨き・読書・深呼吸)を行うことで脳に「寝る時間」を認識させる
まとめ
不眠は生活習慣、心理状態、環境など複合的な要因が絡む問題ですが、原因を理解して改善策を実践することで質の高い睡眠が得られます。
- 自律神経を整える
- 就寝・起床リズムを固定
- 環境を整えてリラックス
- 食事・運動・メンタルケアを工夫
短期間で完全に改善するのは難しくても、少しずつ習慣を変えることで、ぐっすり眠れる毎日が手に入ります。睡眠を改善することは、健康だけでなく集中力や生産性、心の安定にもつながる重要な生活習慣です。
この記事は個人で収集した情報をもとに記載していますので、誤った情報を記載している可能性があります。
この記事だけではなく、他の方が公開されている情報もぜひチェックしてみてください