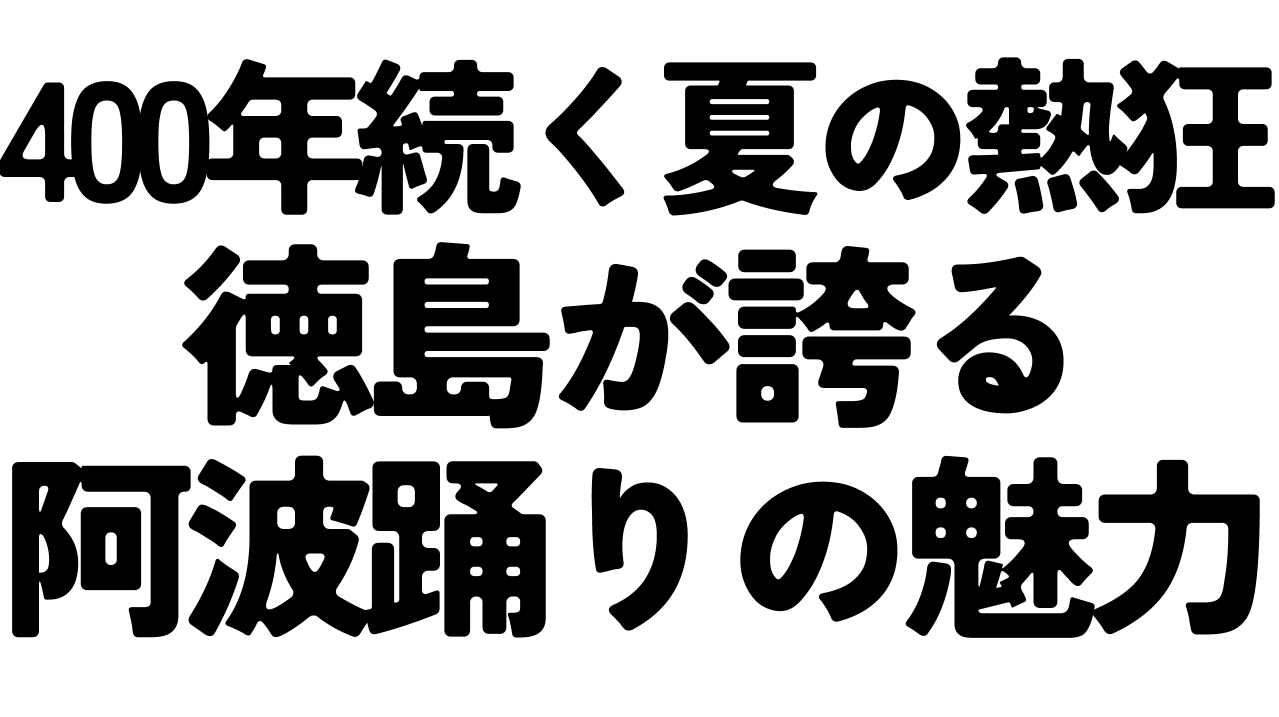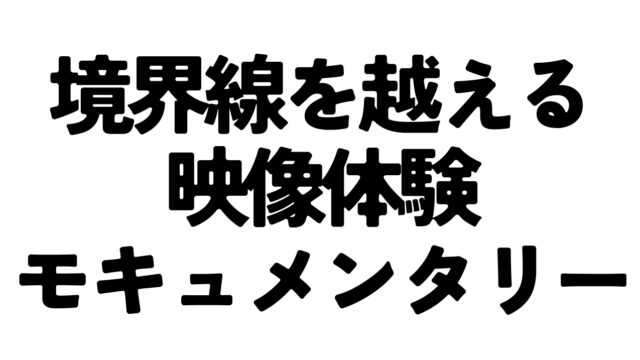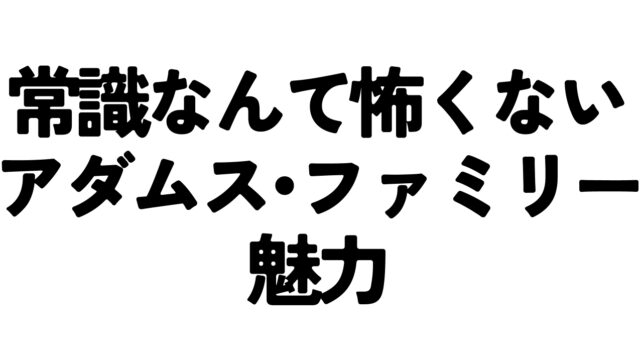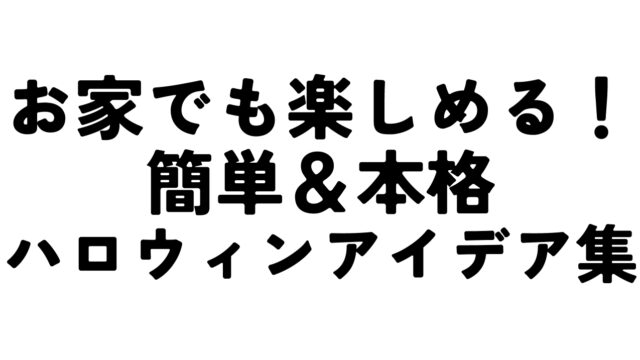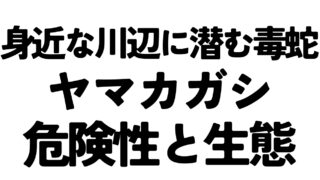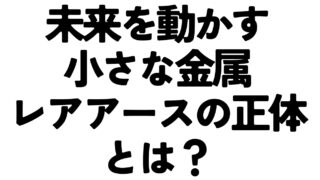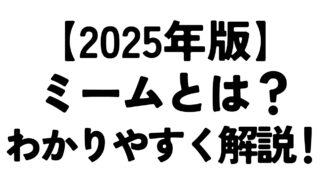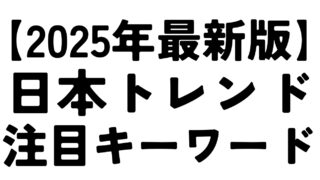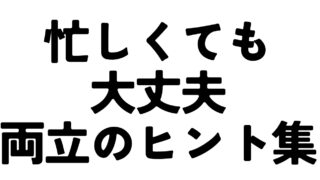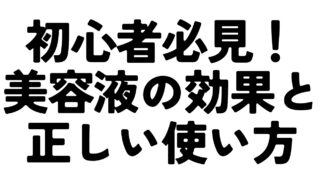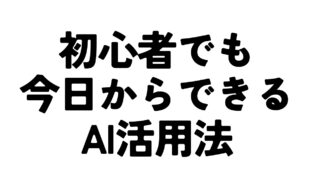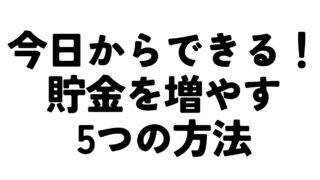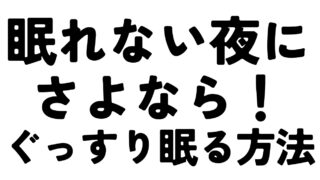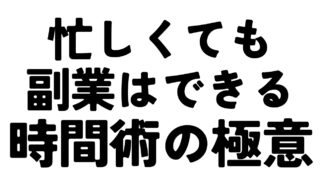日本の夏祭りの中でも、ひときわ華やかで観光客から絶大な人気を集めるのが 徳島県の阿波踊り です。
毎年8月のお盆の時期に開催され、徳島市には国内外から100万人以上の観光客が訪れます。独特の掛け声「踊る阿呆に見る阿呆、同じ阿呆なら踊らにゃ損損」で知られ、踊り手と観客が一体となる光景は圧巻です。
しかし、阿波踊りはただの「観光イベント」ではありません。400年以上の歴史を持つ伝統芸能であり、徳島の文化や人々の暮らしと深く結びついています。
この記事では、阿波踊りの歴史や文化的背景、楽しみ方を詳しく解説します。
阿波踊りの歴史
起源は安土桃山時代
阿波踊りの起源は 16世紀後半、安土桃山時代 にまでさかのぼります。
天正年間(1580年代)、阿波国(現在の徳島県)を治めていた蜂須賀家政が徳島城の落成祝いを催しました。その際、城下の人々が祝いの酒に酔い、踊り騒いだのが阿波踊りの始まりと伝えられています。
この自由奔放な踊りが庶民の間に広がり、やがて徳島独自の「盆踊り」として定着していきました。
江戸時代の阿波踊り
江戸時代になると、阿波踊りはお盆の行事として毎年行われるようになります。藩が規制を設けるほど盛り上がりを見せ、当時から「天下の奇祭」と呼ばれていました。
踊りのスタイルは次第に整えられ、現在のような連(れん)と呼ばれるグループ単位で踊る形が確立していきます。
近代から現代へ
明治以降、阿波踊りは徳島の夏の風物詩として定着。戦後は観光資源として注目され、毎年8月12日〜15日に行われる「徳島市阿波踊り」は日本を代表する夏祭りとなりました。
現在では、東京・高円寺や埼玉・南越谷など全国各地にも広まり、地域ごとに特色ある阿波踊りが開催されています。
阿波踊りの文化的特徴
掛け声とリズム
阿波踊りといえば「ヤットサー! ヤットヤット!」という掛け声。
三味線や太鼓、鉦(かね)による軽快なリズムに乗せ、踊り手が観客を巻き込むように声を合わせます。この独特のリズムが観客の心を高揚させ、祭り全体の熱気を高めます。
男女の踊りの違い
- 男踊り:腰を低く落とし、豪快で力強い動き。扇子や団扇を手に持つことも多い。
- 女踊り:浴衣に編笠をかぶり、しなやかで優雅な動き。両手を高く上げる姿勢が特徴。
この対比が阿波踊りの大きな魅力であり、舞台全体に華やかさを与えます。
連(れん)の存在
阿波踊りは「連」と呼ばれる踊りのグループで構成されます。
有名な連には「阿波の風」「娯茶平」「うずき連」などがあり、各連ごとに衣装や踊りのスタイルが異なります。観客は自分のお気に入りの連を見つけて楽しむのも醍醐味です。
阿波踊りの楽しみ方
1. 徳島市阿波踊りを観に行く
本場の阿波踊りは毎年8月12日〜15日に開催。市内中心部が歩行者天国となり、昼も夜も踊りが続きます。
- 有料演舞場:桟敷席で迫力の舞を間近で観覧可能
- 無料演舞場・街角:観光客も気軽に参加できる
2. 踊る阿呆になる!
観客参加型の「にわか連」に加われば、初心者でもすぐに踊りに参加できます。実際に体を動かしてみることで、阿波踊りの魅力を全身で体感できます。
3. 阿波踊り会館で学ぶ
徳島市の「阿波おどり会館」では、一年中阿波踊りの公演を観覧でき、体験教室もあります。観光シーズン以外でも阿波踊り文化に触れられるおすすめスポットです。
阿波踊りが地域に与える影響
阿波踊りは単なる観光イベントにとどまらず、地域社会に大きな影響を与えています。
- 観光収入:徳島市の阿波踊りは毎年約10億円以上の経済効果を生むとされる
- 地域コミュニティ:連活動を通じ、世代や職業を超えた交流が育まれる
- 文化継承:子ども連や学校教育に取り入れられ、伝統が受け継がれている
まとめ|阿波踊りは歴史と文化が息づく日本の宝
- 阿波踊りは400年以上の歴史を持ち、徳島の文化と深く結びついた祭り
- 掛け声やリズム、男女の踊りの違い、連ごとの個性が大きな魅力
- 観るだけでなく踊る側に参加する体験型祭りとして人気
- 地域経済や文化継承にも貢献する「生きた伝統芸能」
徳島に夏訪れるなら、一度は体験したい阿波踊り。
「見る阿呆」も「踊る阿呆」も同じ阿呆。どうせなら一緒に踊って、日本の夏を満喫してみませんか?
この記事は個人で収集した情報をもとに記載していますので、誤った情報を記載している可能性があります。
この記事だけではなく、他の方が公開されている情報もぜひチェックしてみてください