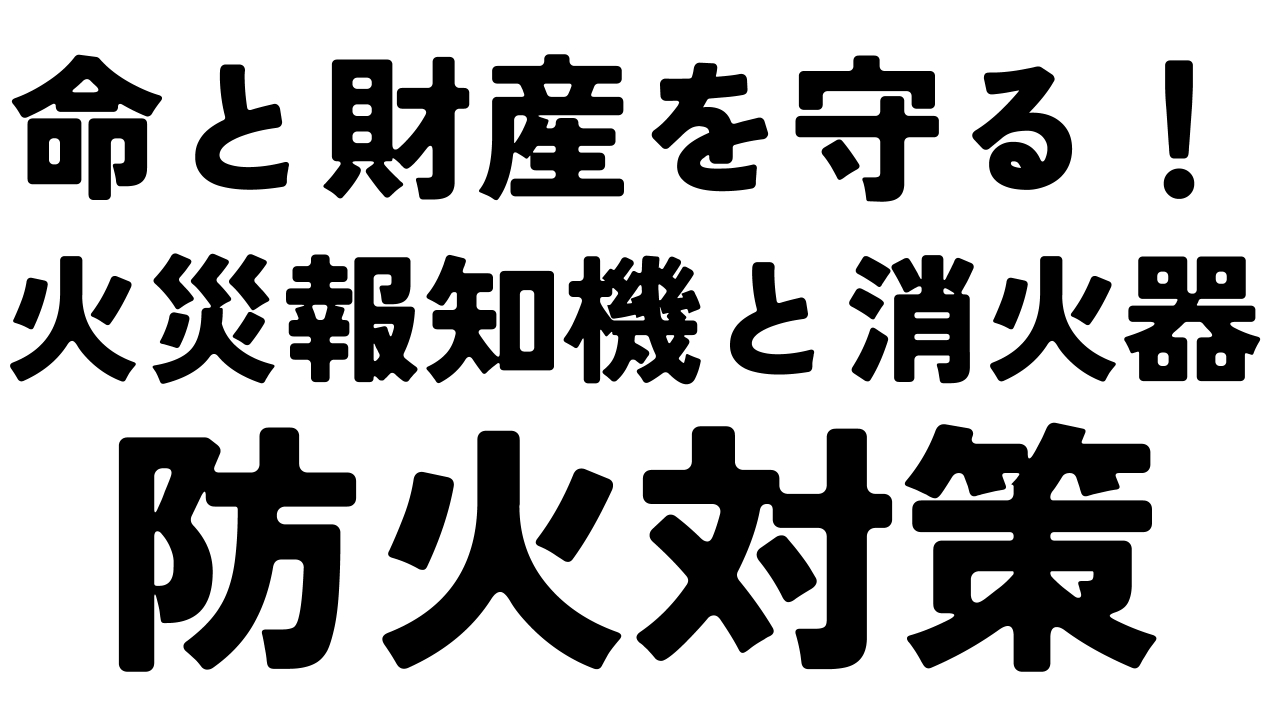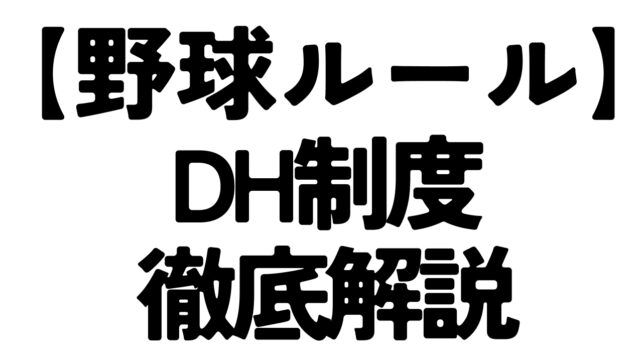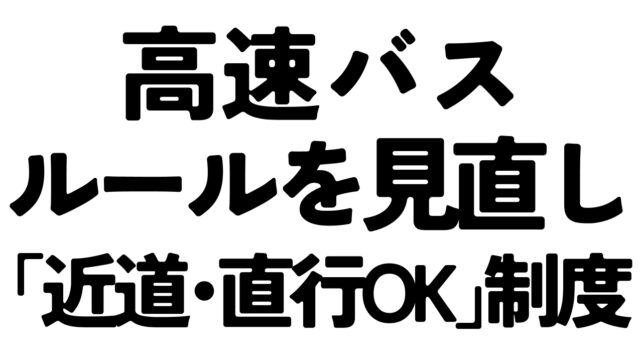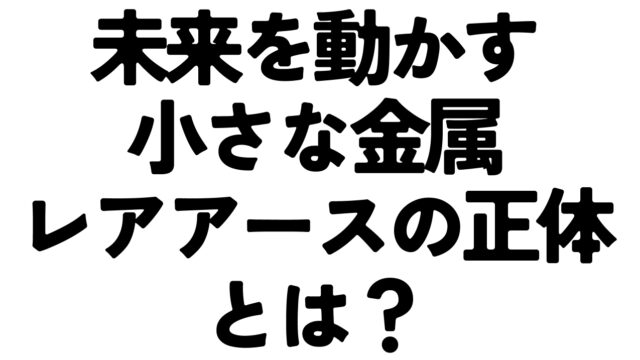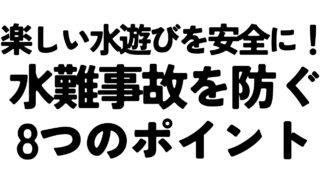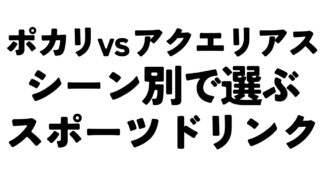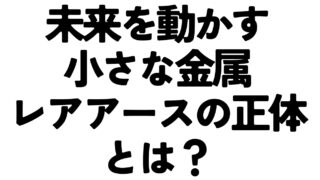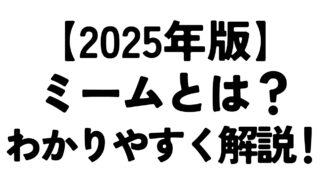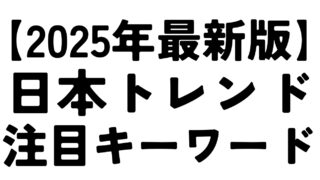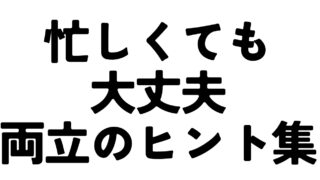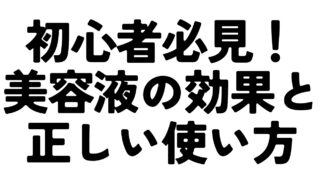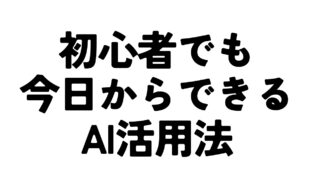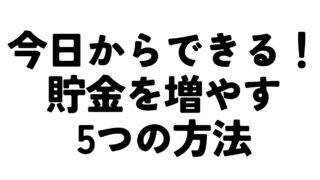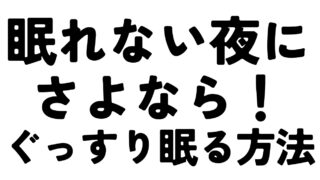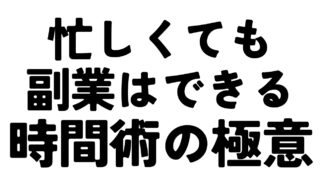近年、日本各地で住宅火災や建物火災が相次ぎ、ニュースでも頻繁に報じられています。火災は一瞬の油断から発生し、わずか数分で人命や財産を奪ってしまう恐ろしい災害です。こうした火災から身を守るために欠かせないのが 火災報知機(住宅用火災警報器) と 消火器 です。
この記事では、火災報知機や消火器の役割と必要性、設置に関する法律やルール、そして実際に家庭や職場でできる防火対策について詳しく解説します。
火災報知機とは?設置の目的と重要性
火災報知機は、火災による 煙や熱を感知して警報を鳴らす装置 です。特に就寝中の火災は気づきにくく、逃げ遅れの原因となります。火災報知機があれば、初期段階で火災を知らせ、迅速な避難を可能にする のです。
火災報知機の種類
- 煙感知式:煙を感知して作動。一般的な家庭に広く普及。
- 熱感知式:急激な温度上昇を感知して作動。キッチンやガレージに適している。
火災報知機の設置義務
日本では2006年の消防法改正により、新築住宅には火災報知機の設置が義務化。さらに2011年6月以降は、既存住宅でも設置が義務となりました。
特に寝室や階段など、避難経路となる場所に設置が求められています。
消火器の役割と必要性
消火器は、火災の初期消火に欠かせない道具 です。火災は発生から3分以内であれば初期消火が可能とされていますが、それを過ぎると一気に燃え広がります。
消火器の種類
- 粉末消火器:広く使われ、家庭・オフィスで一般的。油火災や電気火災にも対応。
- 強化液消火器:天ぷら油火災などに強い。飲食店の厨房に適している。
- 二酸化炭素消火器:精密機器を扱う場所に有効。
消火器の設置基準
- 飲食店やオフィス、集合住宅などでは消防法に基づき設置が義務化。
- 一般家庭でも設置義務はありませんが、台所やガレージなど火気を扱う場所に1本備えておくと安心です。
火災報知機と消火器がない場合のリスク
火災報知機がなければ、煙に気づかず逃げ遅れるリスク が大幅に高まります。実際、総務省消防庁のデータによると、火災報知機が未設置の住宅では 逃げ遅れによる死者数が約2倍 に上ります。
また、消火器がなければ初期消火のチャンスを逃し、消防車が到着する前に火が家全体に広がる 危険性が高まります。
家庭や職場でできる火災対策のポイント
1. 定期的に作動確認を行う
火災報知機は電池切れや故障で作動しない場合があります。半年に一度は確認しましょう。
2. 消火器の有効期限をチェックする
消火器は おおむね5年程度が使用期限。古くなると正常に作動しない場合があります。
3. 避難経路を確認しておく
火災時はパニックになりやすいため、日頃から家族や従業員と避難ルートを確認しておくことが大切です。
4. キッチン火災に注意する
住宅火災の原因で最も多いのが コンロからの出火。調理中にその場を離れない、油を多量に使う際は消火器をそばに置く、などの対策を心がけましょう。
5. 地域の防火訓練に参加する
自治体や消防署で行われる防火訓練は、消火器の使い方や避難方法を学ぶ絶好の機会です。
火災報知機・消火器設置のまとめ
- 火災報知機は 逃げ遅れを防ぐための必需品。法律でも設置が義務化されている。
- 消火器は 初期消火のために不可欠。家庭でも1本常備するのがおすすめ。
- 定期的な点検や訓練を通じて「万が一」に備えることが重要。
火災は「自分の家には関係ない」と思っている家庭ほど、不意に起きるものです。火災報知機と消火器は、家族の命と財産を守るための最低限の備え。ぜひ今日から安全対策を見直してみましょう。
この記事は個人で収集した情報をもとに記載していますので、誤った情報を記載している可能性があります。
この記事だけではなく、他の方が公開されている情報もぜひチェックしてみてください