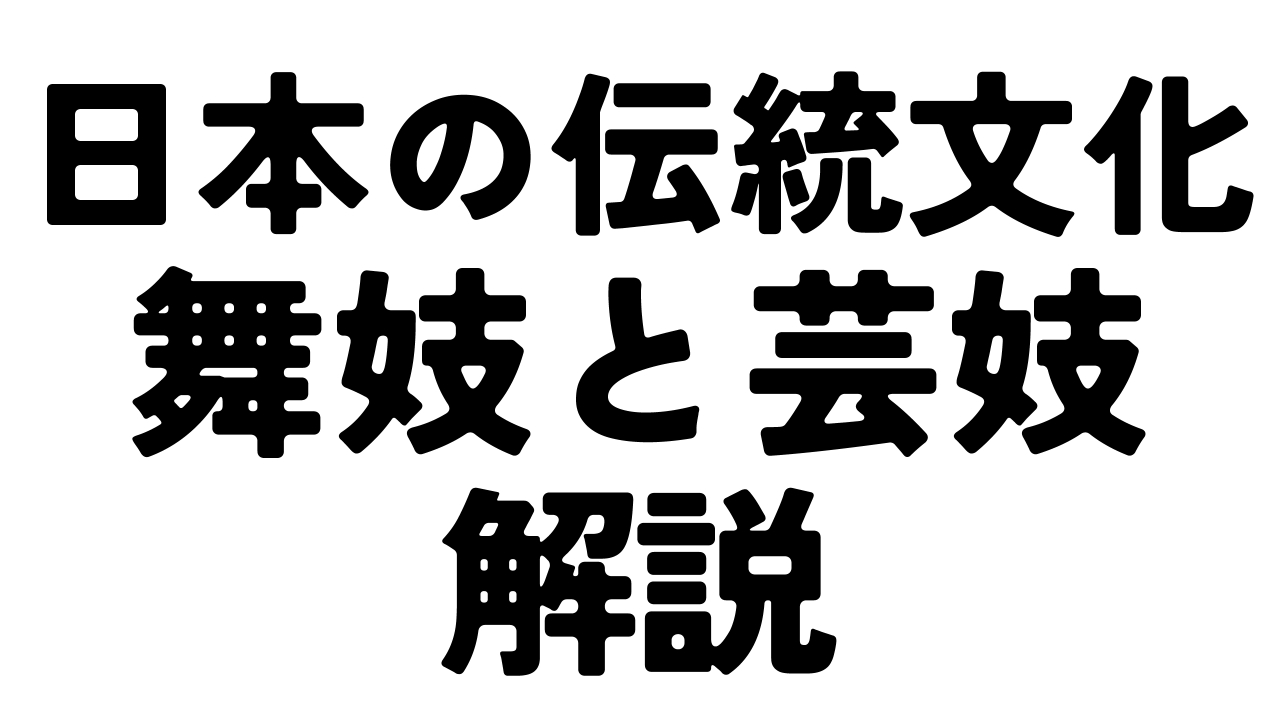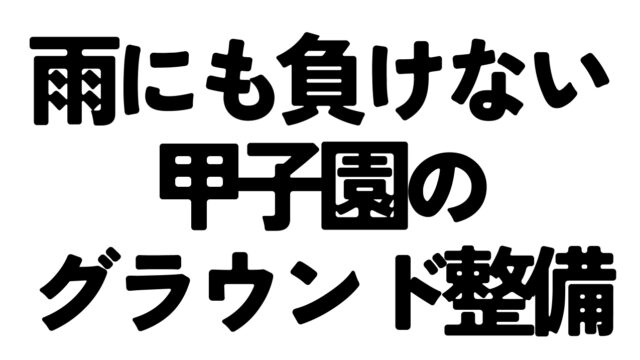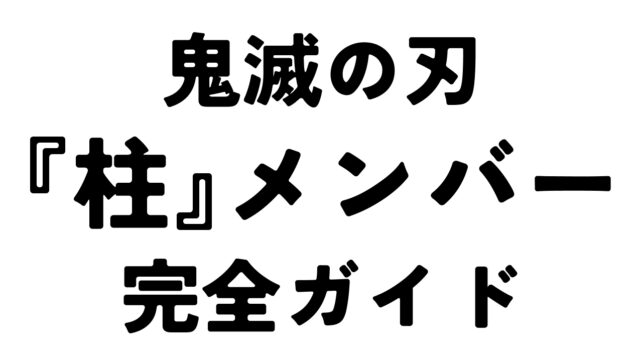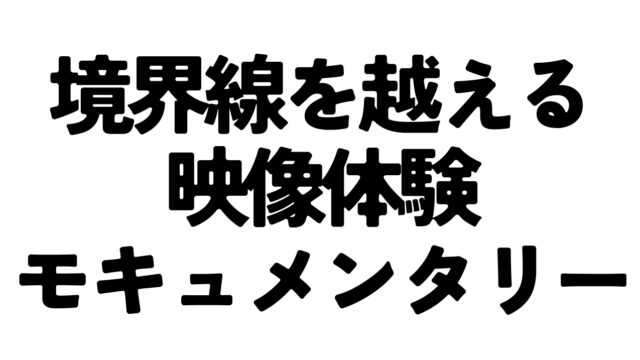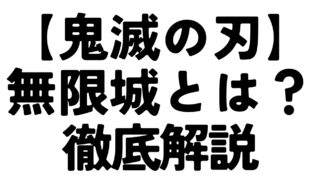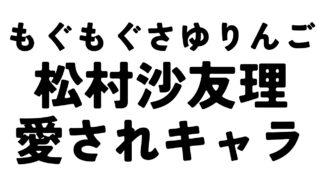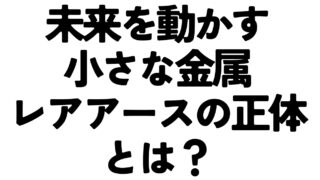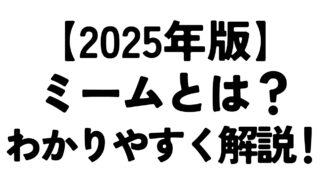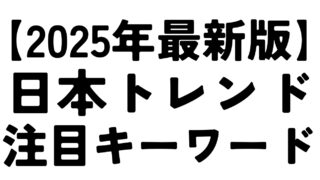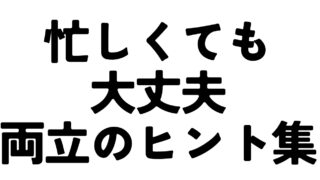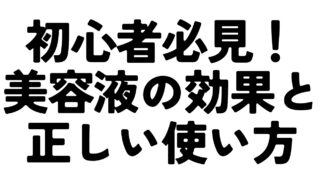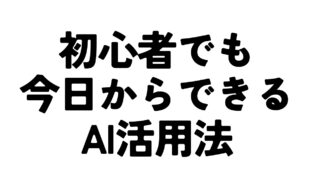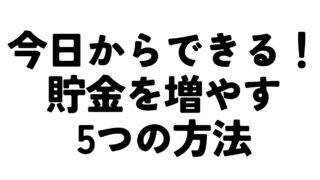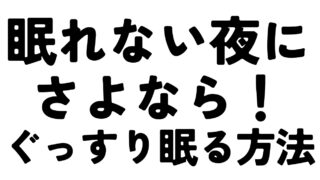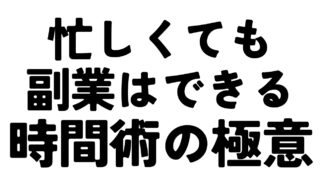京都の花街(かがい)でよく聞く「舞妓さん」と「芸妓さん」。
どちらも日本の伝統文化を代表する存在ですが、実は見た目・年齢・仕事の内容・修行の段階などに明確な違いがあります。
この記事では、舞妓と芸妓の違いを5つのポイントでわかりやすく解説します。
🔰そもそも舞妓・芸妓とは?
両者とも、お座敷(お茶屋など)で客をもてなし、舞や三味線などの芸で楽しませる職業です。
京都では「芸者」という言い方はあまり使わず、以下のように呼ばれます:
- 京都:舞妓(まいこ)/芸妓(げいこ)
- 東京や他地域:芸者(げいしゃ)
では、両者の違いを詳しく見ていきましょう。
🎀 1. 年齢・経験の違い
| 舞妓 | 芸妓 |
|---|---|
| 見習い中(10代中心) | 一人前の芸者(20代〜) |
| 通常15〜20歳前後 | 20歳以降(舞妓から昇進) |
**舞妓は「芸妓になる前の修行期間」**にあたるため、年齢も若く、まだ経験の浅い段階です。
💃 2. 見た目・装いの違い
| 特徴 | 舞妓 | 芸妓 |
|---|---|---|
| 髪型 | 自分の地毛で日本髪 | かつら |
| 着物 | 色鮮やかで袖が長い(振袖) | 落ち着いた色合いの留袖風 |
| 帯 | 長く垂らした「だらりの帯」 | 短めで結び目も簡素 |
| 化粧 | 白塗り+赤・ピンク系の華やかなメイク | 白塗りでも控えめ、または薄化粧の場合も |
舞妓は、より華やかで「少女らしさ」を強調した装い。
芸妓は大人の女性として、落ち着いた雰囲気になります。
🎭 3. 仕事の内容と芸の違い
| 内容 | 舞妓 | 芸妓 |
|---|---|---|
| 主な役割 | おもに舞踊で客をもてなす | 舞・三味線・唄・お座敷芸など幅広くこなす |
| 接客 | 先輩芸妓と一緒に | 単独で対応可能 |
舞妓は、踊りを中心に接客を学ぶ期間。芸妓は、すでにすべての芸を習得していて、プロの芸を提供する立場です。
📅 4. 修行の流れ(京都の場合)
- 仕込み(住み込み見習い・中学生卒業後)
- 見習い舞妓(お披露目前)
- 舞妓デビュー(約5年間)
- 襟替え(えりがえ)で芸妓になる
舞妓から芸妓になることを「襟替え(えりかえ)」と呼び、装いや役割も一気に大人の女性として変化します。
🏮 5. 地域による呼び方の違い
| 地域 | 見習い | 一人前 |
|---|---|---|
| 京都 | 舞妓 | 芸妓(げいこ) |
| 東京 | 半玉(はんぎょく) | 芸者 |
| 金沢 | 茶屋娘 | 芸妓(げいぎ) |
呼び名や制度は地域によって異なるため、「舞妓=京都独特の文化」と言われることも多いです。
✅まとめ|舞妓と芸妓の違いを一言で言うと?
- 舞妓:芸妓を目指して修行中の10代の若い女性。華やかでかわいらしい印象。
- 芸妓:一人前の芸者として、お座敷で本格的な芸を披露するプロフェッショナル。
どちらも日本文化の宝とも言える存在で、伝統を受け継ぐために日々努力を重ねています。
⚠️注意事項
本記事は、京都を中心とした花街文化に基づいて記述しています。他地域では呼称や制度に違いがある場合があります。観光体験などで舞妓や芸妓に会う際は、伝統と敬意をもって接することが大切です。
この記事は個人で収集した情報をもとに記載していますので、誤った情報を記載している可能性があります。
この記事だけではなく、他の方が公開されている情報もぜひチェックしてみてください