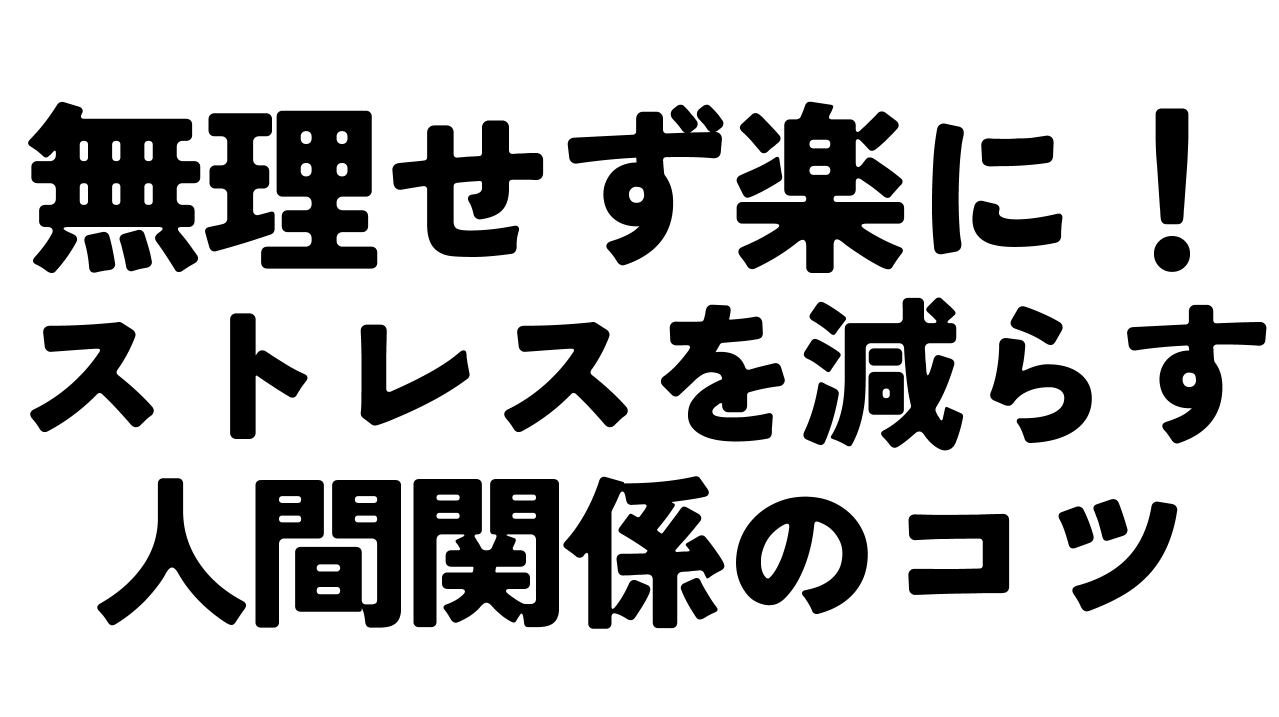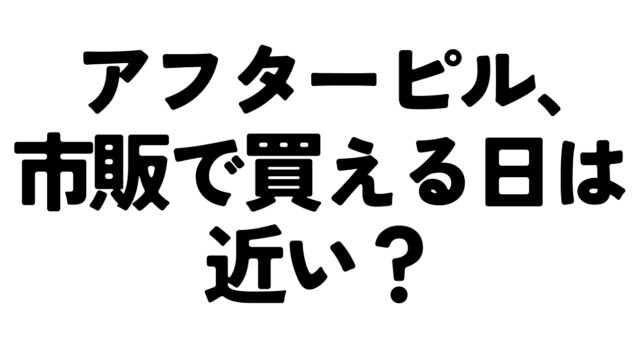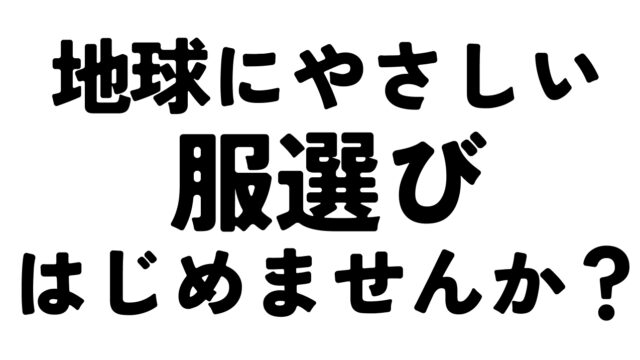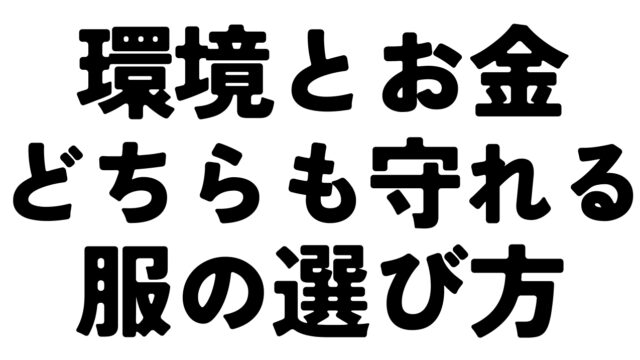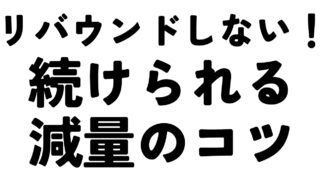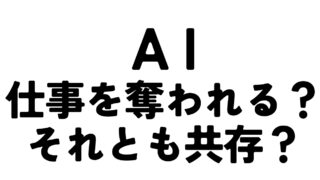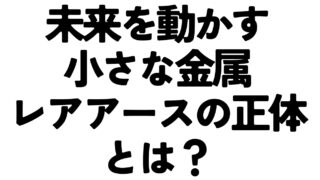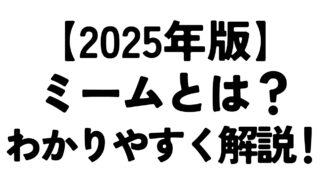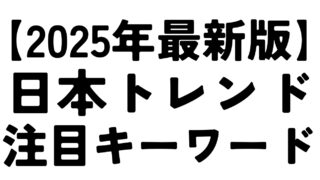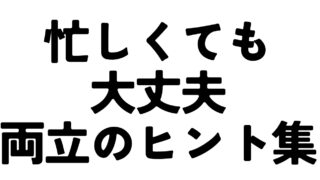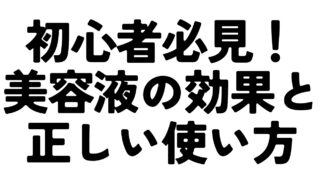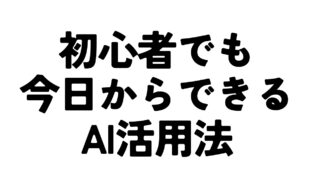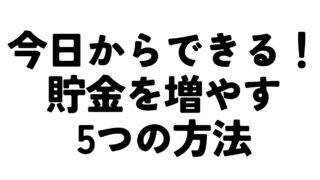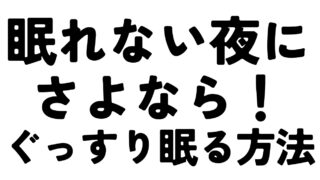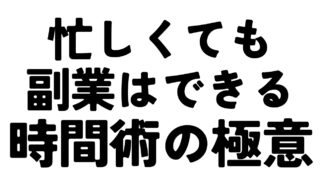職場、友人関係、家族…。人は誰しも人間関係の中で生きています。しかし「気を遣いすぎて疲れる」「人といると消耗してしまう」と感じる方も少なくありません。なぜ人間関係はこんなにも疲れるのでしょうか?
本記事では、人間関係に疲れる心理学的背景、ストレスへの対処法、そして心を軽くするコミュニケーション術や考え方について詳しく解説します。
なぜ人間関係に疲れてしまうのか?心理学的背景
1. 承認欲求と比較のストレス
人は誰しも「認められたい」という承認欲求を持っています。しかしSNSや職場では常に他人と比較する状況が多く、「自分は劣っている」と感じてしまうことでストレスが溜まります。
2. 相手に合わせすぎる「過剰適応」
心理学では、自分の気持ちを抑えて相手に合わせすぎることを「過剰適応」と呼びます。一見、円滑な関係を築けているように見えても、心の中に不満や疲労が蓄積していきます。
3. 境界線(バウンダリー)の欠如
自分と相手の境界があいまいだと、相手の感情に振り回されやすくなります。「嫌われないように」と考えすぎると、自己犠牲的になり疲労が増します。
4. コミュニケーションスタイルの違い
人には「話すのが好きなタイプ」と「聞くのが好きなタイプ」など、性格や文化の違いがあります。スタイルが合わない相手とのやり取りは、それだけで消耗の原因となります。
5. ネガティビティ・バイアス
人間は本能的に「ネガティブな情報に強く反応する」傾向があります。相手の一言に敏感に反応してしまい、人間関係が疲れる原因になるのです。
人間関係の疲れを和らげるストレス対処法
1. 自分の気持ちを客観視する「アサーション」
アサーションとは「自分も相手も大切にする自己表現」のこと。相手に合わせるだけでもなく、自己主張だけでもない、バランスの取れたコミュニケーションを心がけるとストレスが減ります。
2. 物理的な距離を取る
疲れる相手とは、無理に一緒にいる必要はありません。適度に距離をとることで心の余裕が戻ってきます。
3. 完璧な人間関係を目指さない
「みんなに好かれたい」と思うほど、人間関係は苦しくなります。心理学的にも、どんな人間でも「自分を好意的に見る人」と「そうでない人」が必ず存在することがわかっています。
4. 趣味や運動でリフレッシュする
人間関係の疲れは、人とのやり取りに集中しすぎて「自分自身をケアできていない」状態から来ることも多いです。運動や趣味で気分転換をしましょう。
5. 感情を書き出す「ジャーナリング」
イライラや不安をノートに書き出すことで、自分の感情を整理できます。心理療法の一つとしても注目されています。
心が軽くなるコミュニケーション術
1. 「聴く力」を意識する
自分が話さなければと思うと疲れます。むしろ「聴く」側に回ることでプレッシャーが減り、自然な関係を築きやすくなります。
2. 共感の言葉を使う
「わかるよ」「大変だったね」といった共感は、相手との距離を近づける魔法のフレーズです。相手も安心し、自分も無理に話題を広げなくて済みます。
3. 小さな「NO」を言えるようにする
全部のお願いを引き受ける必要はありません。「今日は難しいけど、来週ならできるよ」など、やんわり断る練習をしましょう。
4. ユーモアを交える
真面目すぎる会話は緊張を生みます。ちょっとした冗談や笑顔を交えることで空気が和らぎます。
5. 自分を守る境界線(バウンダリー)を持つ
「ここから先は踏み込ませない」というラインを持つことで、必要以上に相手に振り回されなくなります。これは自分を大切にすることにもつながります。
自分を守る考え方
1. 「人は人、自分は自分」
他人と比べるほど疲れます。相手は相手、自分は自分と割り切るだけで気持ちが軽くなります。
2. 「嫌われる勇気」を持つ
心理学者アドラーが説いたように、「他人の期待に応え続ける」必要はありません。自分の価値観を大切にする勇気を持ちましょう。
3. 「適切な距離感が健康的な関係をつくる」
親しい間柄でも、常にベタベタしていると疲れます。適度な距離感こそ長続きする関係の秘訣です。
まとめ
人間関係に疲れるのは、心理的な欲求や習慣が影響しているからです。
しかし、過剰に合わせず、自分の感情を大切にし、無理のない距離感を持つことで、心はぐっと軽くなります。
「人間関係は頑張るものではなく、楽しむもの」。
そう思えるように、自分を守る考え方とストレス対処法を生活に取り入れてみてください。
この記事は個人で収集した情報をもとに記載していますので、誤った情報を記載している可能性があります。
この記事だけではなく、他の方が公開されている情報もぜひチェックしてみてください