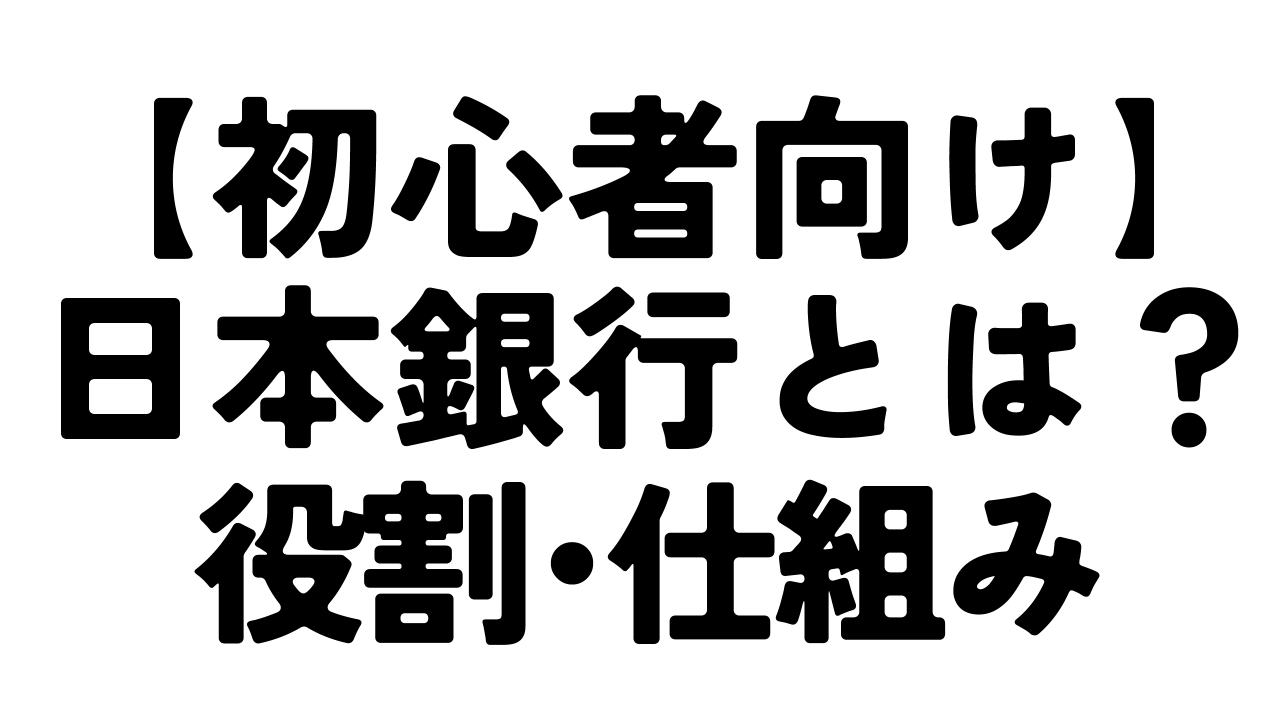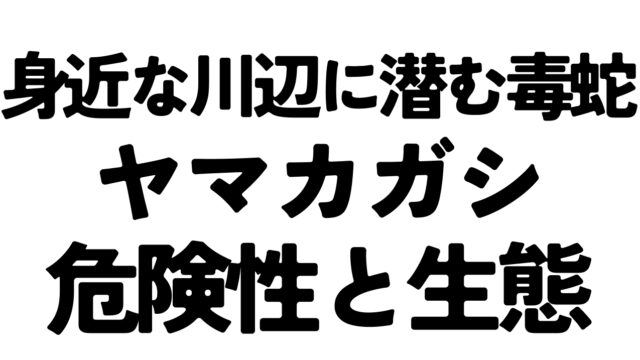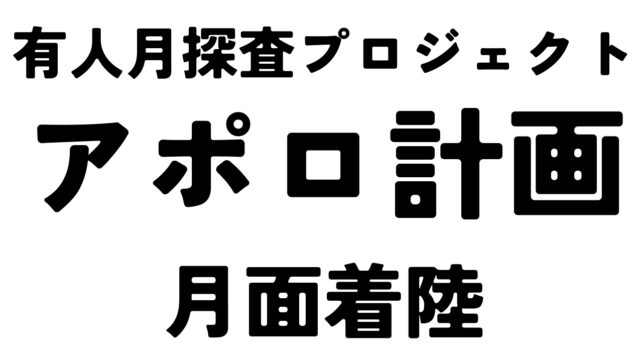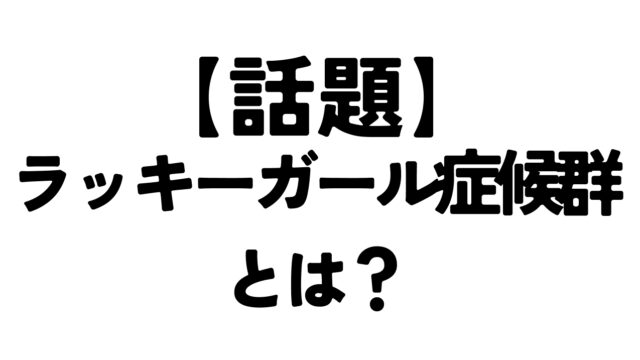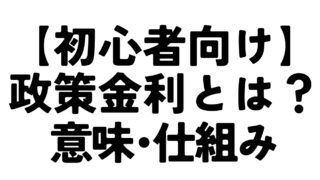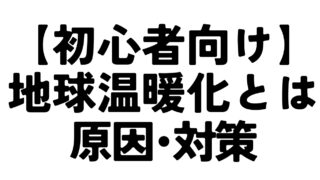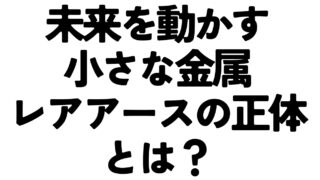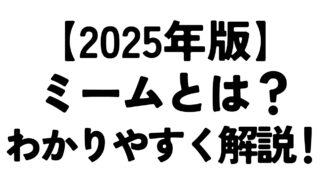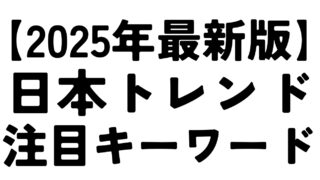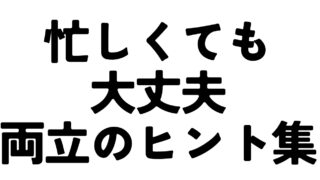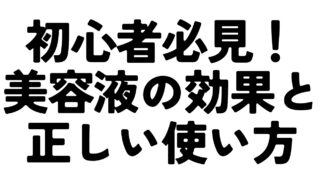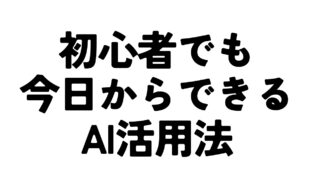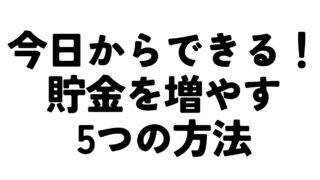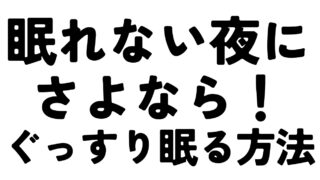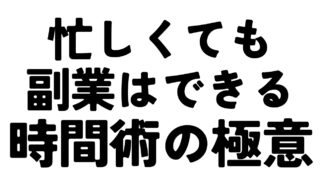「日銀が政策金利を変更」「日本銀行が金融緩和を決定」など、ニュースでよく耳にする日本銀行(にっぽんぎんこう・にほんぎんこう)。でも、それが私たちの生活にどう関わっているのか、具体的にイメージしづらい人も多いのではないでしょうか?
この記事では、日本銀行の役割・特徴・仕組み・経済への影響を初心者にもわかりやすく解説します。
✅日本銀行とは?ひとことで言うと…
日本銀行(通称:日銀)は、日本の**中央銀行(ちゅうおうぎんこう)**です。
つまり、「お金の供給・金融のコントロール・経済の安定」を担う、**国の経済の“司令塔”**のような存在です。
創設は1882年(明治15年)。本店は東京・日本橋にあります。
🏦日本銀行の3つの主な役割
①「物価の安定」と「金融政策の運営」
日銀の最重要任務は、**物価の安定(インフレ・デフレを防ぐ)**です。
そのために行うのが「金融政策」で、具体的には:
- 政策金利の調整
- 国債の買い入れ
- マネーサプライ(通貨量)の管理
たとえば、景気が悪くなれば金利を下げてお金を流通させ、景気が過熱すれば金利を上げて抑えるといったように、経済の温度調整を行っています。
②「お金の発行と管理」
日本で使われる紙幣(お札)を発行しているのは日銀です。
つまり、「1万円札・5千円札・千円札などの製造元は日銀」なのです。
また、古くなった紙幣を回収し、新しいお札と交換する管理業務も担っています。
③「銀行の銀行」としての機能
日銀は、私たちが利用する「みずほ銀行」「三菱UFJ銀行」などの銀行にとっての銀行でもあります。
- 民間銀行が日銀にお金を預けたり、借りたりする
- 銀行同士のお金のやり取りを日銀が仲介する
これにより、金融システム全体がスムーズに回るようにコントロールされています。
💹日銀の政策が生活にどう関係あるの?
「自分には関係ない」と思われがちですが、実は私たちの暮らしや家計に直結しています。
| 日銀の行動 | 私たちへの影響例 |
|---|---|
| 金利を下げる | 住宅ローンが安くなる、株価が上がりやすい |
| 金利を上げる | 物価の上昇が抑えられる、円高になる |
| 通貨供給量を増やす | 消費が促進されて景気が上がる |
| 通貨供給量を減らす | 景気が冷え、インフレを防止する |
たとえば、2024年には日銀がマイナス金利政策を解除したことで、住宅ローンの金利上昇や円高傾向が話題になりました。
🌍世界の中央銀行と比較
日本銀行は、日本の中央銀行として独立性を持っています。同様に、世界には以下のような中央銀行があります。
| 国・地域 | 中央銀行名 | 略称 |
|---|---|---|
| アメリカ | 連邦準備制度理事会 | FRB |
| ユーロ圏 | 欧州中央銀行 | ECB |
| イギリス | イングランド銀行 | BOE |
各国の中央銀行も同じように、金利を操作してインフレや景気を調整しています。
📌まとめ|日本銀行を知れば、経済ニュースがわかる!
日本銀行(日銀)は、日本経済の舵取りをしている超重要な機関です。
私たちの生活の中では目に見えない存在かもしれませんが、
- 金利
- 景気
- 為替
- 物価
- 株価
など、暮らしのお金のすべてに深く関係しています。
政策金利や金融政策に関心を持つことで、家計管理や資産運用にも役立つ情報が読み解けるようになります。
⚠️注意事項
本記事の内容は2025年時点の情報をもとに作成しています。金融政策や日本銀行の動向は経済状況によって随時変化しますので、最新の情報は日本銀行公式サイトまたは経済ニュースをご確認ください。
▶ 公式サイト:https://www.boj.or.jp
この記事は個人で収集した情報をもとに記載していますので、誤った情報を記載している可能性があります。
この記事だけではなく、他の方が公開されている情報もぜひチェックしてみてください