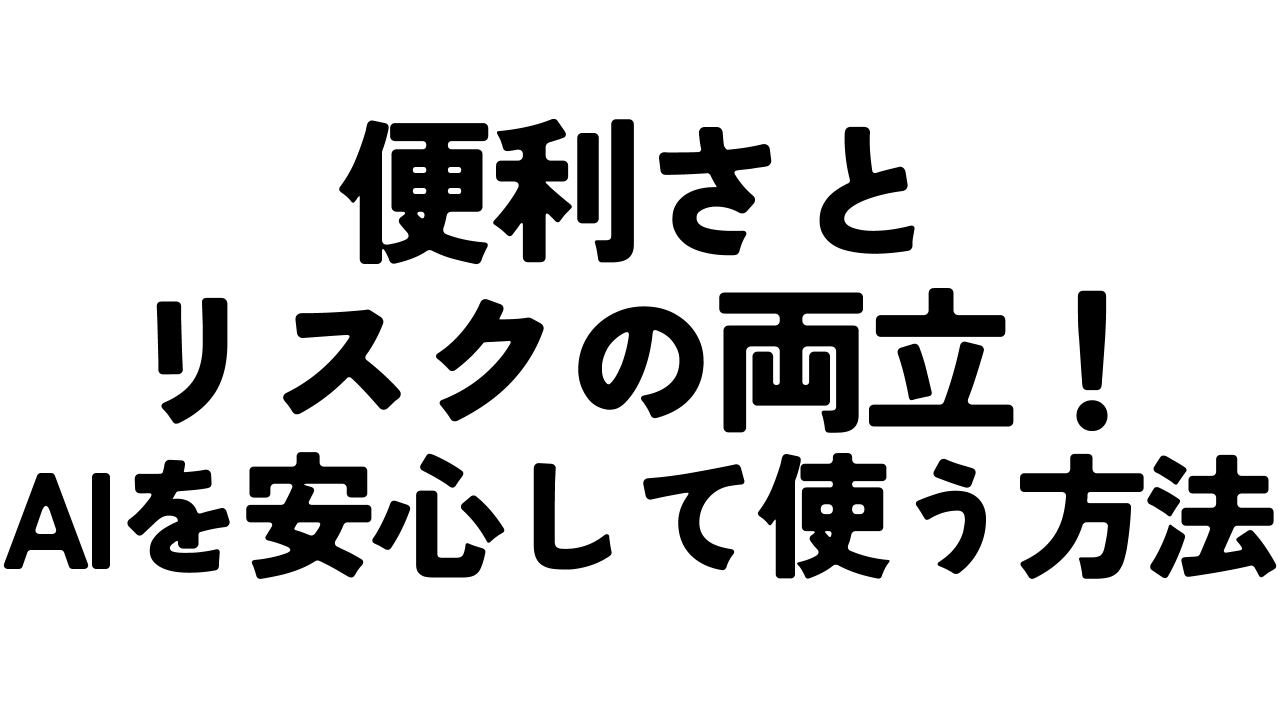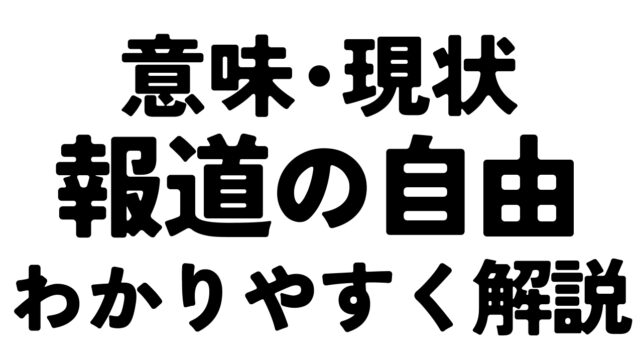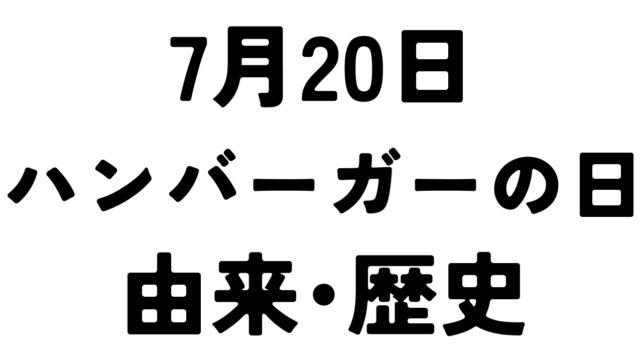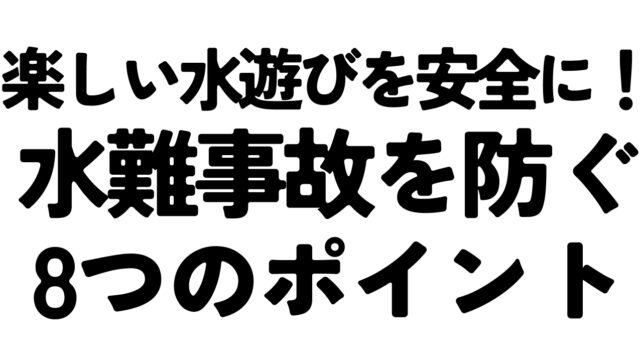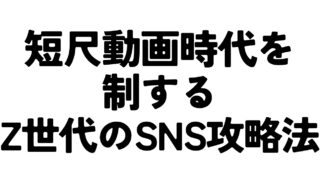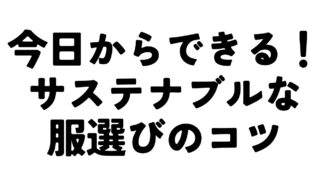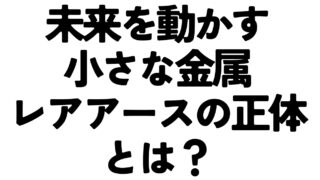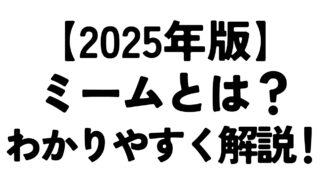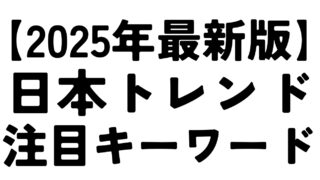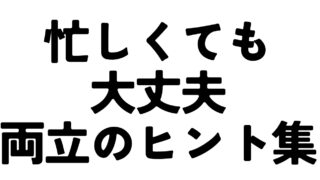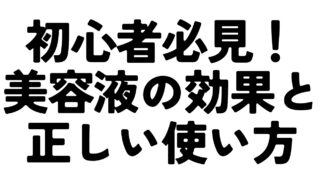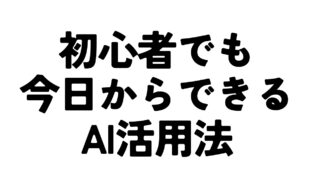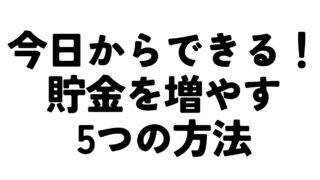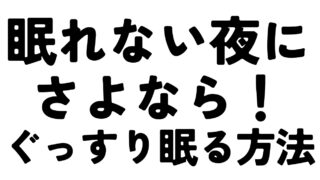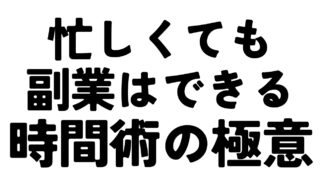近年、ChatGPTをはじめとする「生成AI」が急速に普及し、仕事や学習、日常生活のさまざまな場面で活用されるようになりました。しかし便利さの一方で、「情報はどこまで安全なのか?」「入力したデータは漏れないのか?」と不安に思う人も少なくありません。この記事では、生成AIを安全に使うための注意点やリスク対策をわかりやすく解説します。
生成AIの仕組みと情報リスク
生成AIは膨大なデータを学習して文章や画像を生成します。ユーザーが入力したテキストはサービスの改善やモデルの学習に利用される可能性があるため、企業秘密や個人情報を入力するのは非常に危険です。
また、インターネットと連動したサービスでは、入力内容がクラウドに保存されるため、万が一の情報漏洩リスクも考えられます。
生成AI利用時の主なリスク
- 個人情報の流出
氏名・住所・電話番号・口座情報などを入力すると、外部に保存される可能性があります。 - 企業秘密の漏洩
社内の機密資料や未発表のプロジェクト内容を入力すると、第三者に利用されるリスクがあります。 - 不正確な情報の拡散
生成AIは常に正しい情報を提供するわけではありません。誤情報をそのまま利用すれば、信用問題に発展することも。 - 利用規約違反
サービスによっては入力禁止事項があり、違反するとアカウント停止につながる可能性もあります。
安全に利用するための具体的な対策
1. 個人情報を入力しない
生成AIに名前・住所・連絡先・クレジットカード番号などを絶対に入力しないようにしましょう。
2. 機密情報を扱わない
ビジネス利用の際は、未公開の契約書や顧客データを入力するのは避けましょう。代わりに架空データやサンプルを使うのが安全です。
3. 情報の二次確認を徹底する
生成AIの出力内容は一次情報ではないため、そのまま鵜呑みにせず、公式サイトや専門書などで裏付けを取りましょう。
4. セキュリティ設定を確認する
一部の生成AIサービスでは、入力履歴を保存しない設定や「学習に利用しない設定」が選べる場合があります。利用前に必ず確認しましょう。
5. 業務利用は企業ガイドラインを守る
多くの企業では生成AI利用に関する規定を設けています。ガイドラインを守ることで、情報漏洩やコンプライアンス違反を防ぐことができます。
生成AIを安心して活用するコツ
- アイデア出しや文章構成の補助に使う
→ 創造性や発想力を広げる使い方は安全性が高い。 - 一般的な知識整理に利用する
→ 歴史・科学・生活ハックなど公開情報の範囲なら安心。 - プログラミングや翻訳のサポートに活用
→ 機密情報を含まない範囲なら効率化に役立つ。
今後のAIと安全性の展望
各社はセキュリティ強化に取り組んでおり、**「オンプレミス環境で使えるAI」や「個人データを学習に使わないAI」**の開発が進んでいます。将来的には、より安心して利用できる環境が整うと考えられます。
まとめ
生成AIは便利なツールですが、使い方次第で大きなリスクも伴います。
- 個人情報・機密情報は入力しない
- 出力情報は必ず裏取りする
- サービスのセキュリティ設定を確認する
この3つを徹底することで、安心してAIを活用できます。正しく使えば、生成AIは生活や仕事の強力なサポーターとなるでしょう。
この記事は個人で収集した情報をもとに記載していますので、誤った情報を記載している可能性があります。
この記事だけではなく、他の方が公開されている情報もぜひチェックしてみてください