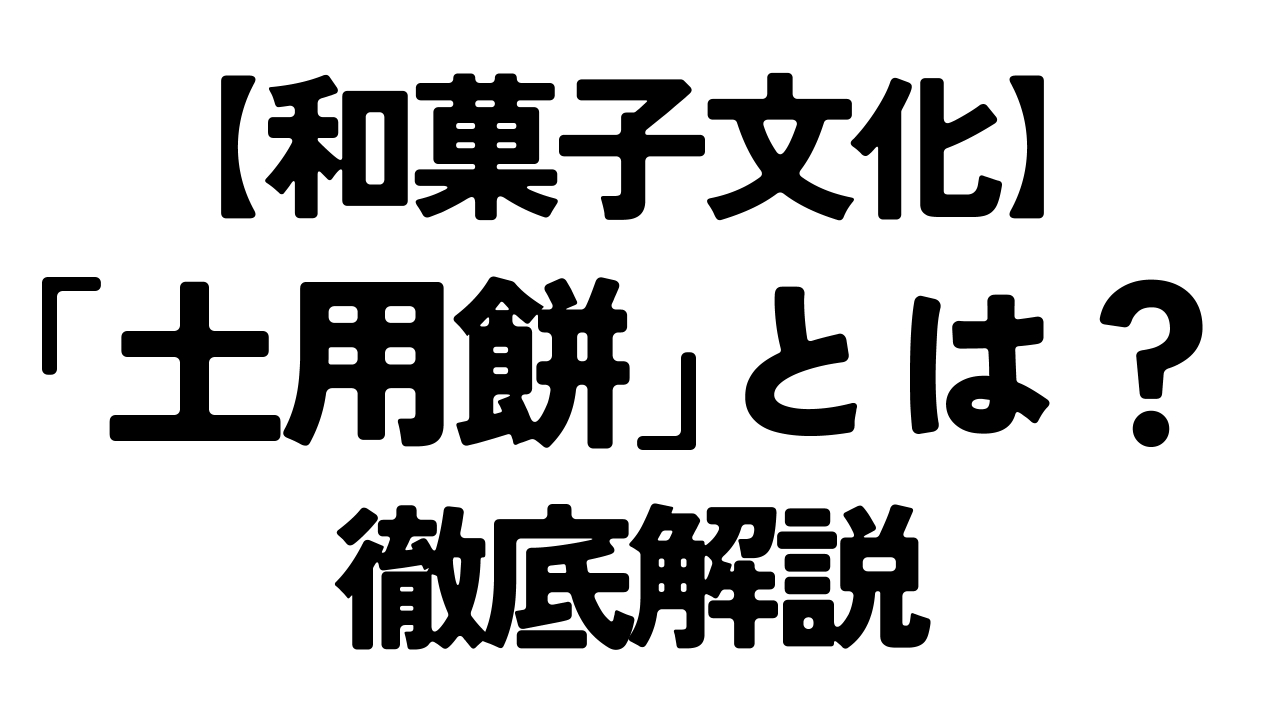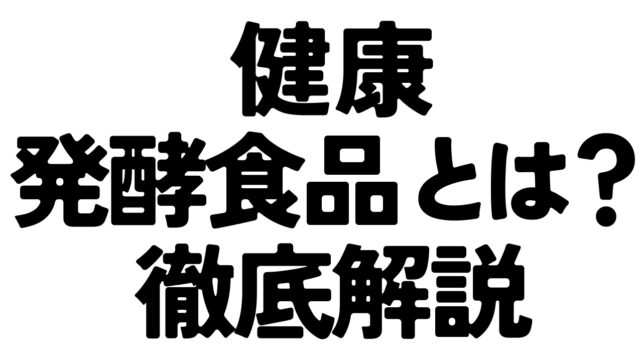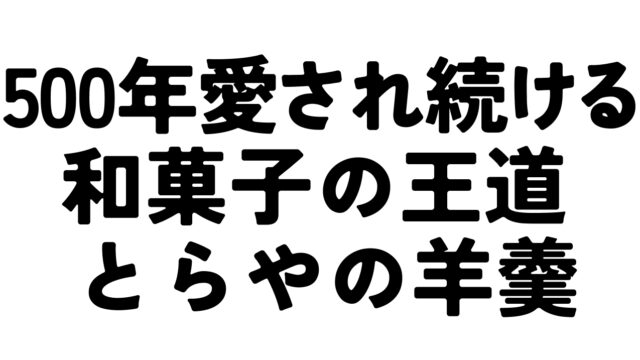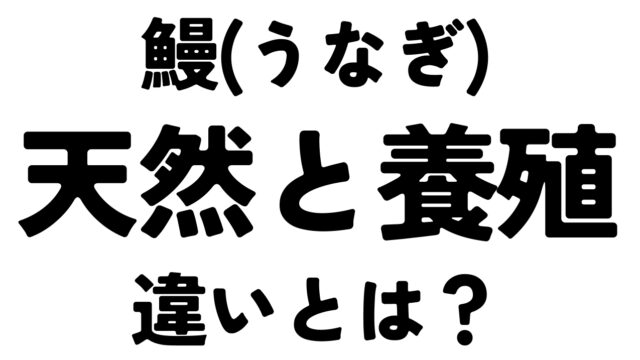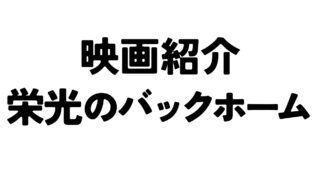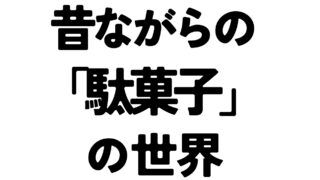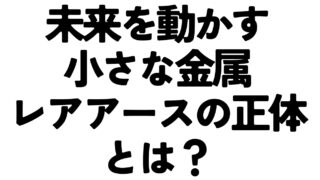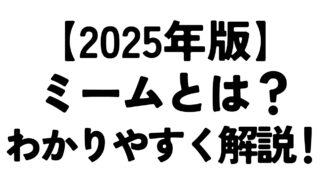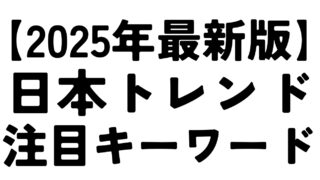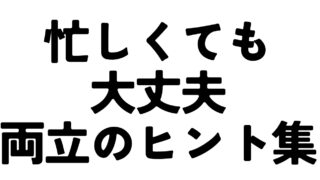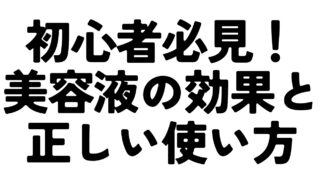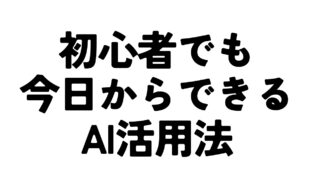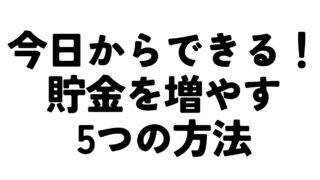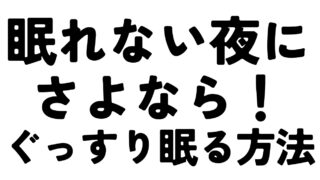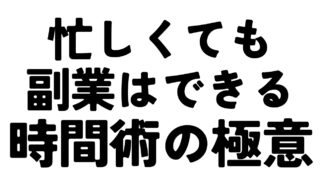みなさんは「土用餅(どようもち)」をご存知ですか?
「土用の丑の日」といえば「うなぎ」が有名ですが、実はもう一つ、日本には古くから伝わる風習があります。それが――土用餅です。
この記事では、土用餅の意味・由来・いつ食べるか・なぜ食べるか、さらに現代風の楽しみ方まで、詳しく解説していきます。
■ 土用餅とは?
「土用餅」とは、主に関西地方などで食べられてきた小豆餡で包まれたお餅のこと。
代表的なのは、「あんころ餅(こしあん or 粒あん)」のような形をしており、もち米の白い餅を甘い餡で包んでいます。
▶ 土用の時期に食べることで、以下のような意味が込められています:
- 暑気払い(暑さから身を守る)
- 無病息災(病気にならない)
- 精をつける(滋養強壮)
- 邪気払い(小豆の赤色は魔除けの象徴)
■ 土用餅を食べるタイミングはいつ?
「土用餅」は、夏の**土用の丑の日(どようのうしのひ)**に食べるのが習わしです。
☀ 2025年の「夏の土用の丑の日」は…
2025年の夏の土用の丑の日は、以下の2日です:
- 一の丑:7月19日(土)
- 二の丑:7月31日(木)
この日に、あんころ餅や土用餅を食べると、「夏バテ知らずで元気に過ごせる」と言われています。
■ 土用餅の由来|なぜ小豆餅なの?
小豆には古来より「魔除け」の力があるとされてきました。特に赤色は邪気を払う色とされ、祝い事や厄除けによく使われます。
また、餅=「力持ち」や「力をつける」といった意味が込められており、「あずき餡 × 餅」は最強の組み合わせ!
つまり…
「あずきのパワー」と「餅の力」を一緒に取り入れて、夏の厳しさに負けない体を作る。
というのが、土用餅を食べる目的なのです。
■ 地域によって違う土用餅のスタイル
地域によって呼び名や食べ方にも違いがあります。
| 地域 | 呼び名 | 特徴 |
|---|---|---|
| 関西 | 土用餅 | こしあんのあんころ餅が主流 |
| 京都 | 土用餅 | 和菓子店が限定販売することも |
| 関東 | あんころ餅、特別な習慣は薄め |
特に京都や大阪の和菓子屋さんでは、土用餅が季節限定商品として登場することも多く、風情があります。
■ 土用餅の楽しみ方アイデア
✅ 冷やして食べる
冷蔵庫で少し冷やすと、暑い日にもぴったり。
✅ 抹茶と合わせて
濃い抹茶と甘い餡の相性は抜群。おうちでちょっとした茶会気分に。
✅ 黒ごまやきなこをトッピング
自分好みにアレンジして楽しむのもおすすめ。
■ おすすめの購入方法
- 和菓子専門店(例:鶴屋吉信、仙太郎、とらや)
- 百貨店の季節和菓子コーナー
- ネット通販(「土用餅 通販」で検索)
最近では楽天やAmazonでも「土用餅」や「季節限定のあんころ餅」が販売されています。
■ 最後に|うなぎだけじゃない!「和菓子の土用習慣」を味わおう
土用の丑の日は「うなぎ」だけが注目されがちですが、日本の食文化にはもっと奥深い風習があります。
「土用餅」は、体をいたわり、無病息災を願う、優しい和の知恵。
今年の土用には、ぜひ一つ「土用餅」を味わってみてはいかがでしょうか?
小さな和菓子に込められた、先人たちの思いにきっと癒されるはずです。
この記事は個人で収集した情報をもとに記載していますので、誤った情報を記載している可能性があります。
この記事だけではなく、他の方が公開されている情報もぜひチェックしてみてください